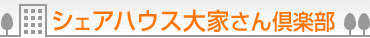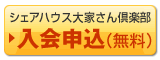第136回 「不都合な真実」とシェアハウス
5月15日、トルコのイスタンブールで2022年春以来3年ぶりに開催される予定だったロシアとウクライナとの直接交渉は、ウクライナ側のゼレンスキー大統領が「停戦にはプーチン大統領と合意しなければならない」と言明したのに対し、ロシア側は政府筋から「プーチン大統領は交渉に参加しない」と発表。このやりとりに、「助けになると思えば飛んでいく」と言っていた米トランプ大統領も、一転して「プーチンと私が会うまでは何も起こらないだろう。プーチンは私が行かないから、(交渉に)行かないことにしたんだ」などと言いだします。トランプ大統領の自己認識はともかく、当事者であるウクライナとロシアの温度差は如何ともしがたく、16日に延期された直接交渉は結局、両大統領不在で行われることに。その結果、今回の直接交渉で状況が劇的に変化する可能性はほとんどなくなってしまいましたが、戦争状態が続く両国が曲がりなりにも直接交渉を再開するということは、小さな一歩ではあるかもしれません。
一方、4月下旬よりカシミール地方で武力衝突が続いていたインドとパキスタンは、5月10日に停戦合意が実現したものの、今なお両国の間で緊張状態が続き、一触即発が懸念されています。世界を覆うキナ臭い空気は、まだまだ収まる様子が一向に見えてきません……。
さて、気を取り直して、今月もシェアハウス大家さんにとって気になるニュースをいくつか取り上げてみたいと思います。まずは、5月13日付の『時事通信』で報じられた「金融庁、スルガ銀に報告徴求=不正融資問題長期化で」( https://www.jiji.com/jc/article?k=2025051301284&g=eco )というニュースから。短い記事なので、以下に全文を引用します。
「スルガ銀行は13日、投資用のアパートやマンションへの不正融資問題を巡り、金融庁から銀行法に基づく報告徴求命令を受けたと発表した。金融庁は、全ての債務者の個別解決に至らず、対応が長期化していることを問題視。早期解決に向けて具体的な改善策の報告を求めた。
スルガ銀は「報告徴求を真摯に受け止め、適時適切な情報開示を行う」とコメント。相談窓口の拡充や個別対話の呼び掛けなどを通じ、解決の加速化を図る方針だ。
スルガ銀では2018年、シェアハウスなど投資用不動産を巡る不正融資が発覚。ガバナンス(企業統治)体制の強化といった再発防止策を進めるとともに、債権の一括譲渡も行い、シェアハウス問題は解決したとしている」
懐かしい――といってはさすがに語弊があるでしょうが、ひさびさに耳にする話題です。もはや固有名詞さえ記事中には見当たりませんが、言うまでもなく「かぼちゃの馬車」事件に端を発する、一連のスルガ銀不正融資問題の続報に当たります。記事中でも「シェアハウス問題は解決した」云々、というスルガ銀側の主張を取り上げていますが、当コラムでも以前、この問題については「解決した」旨の被害者の会側の見解を取り上げたことがあります。損害賠償請求を起こしていた被害者の会側の弁護士が「解決した」とコメントするのであればまだしも納得できますが、これを加害者であるスルガ銀側が口にするのは「ちょっと違うんじゃないか?」と言いたくもなります。最終的に原告が訴訟を取り下げたとしても、訴訟を起こしたという事実そのものが消滅するわけではありません。ましてや、不正融資を行ったという事実が「なかったこと」になるわけでもない。この件に限らず、日本では裁判が終わったとたん「禊(みそぎ)は済んだ」とばかりに、たちまち裁判以前の状況に逆戻りしてしまう事例がしばしばあります。その意味で、金融庁の今回の対応は「理に適った」ものだということができますし、「やらかしてしまった側」であるスルガ銀が「問題は解決した」などと主張するのは、いささか事実認識が甘い、と言わざるを得ないでしょう。
続いて、『朝日新聞デジタル』が5月6日付で報道した「シェアハウス人気、家賃高騰が背景 ホテル代わりに使う訪日外国人も」( https://www.asahi.com/articles/AST521W23T52OXIE046M.html )という記事を見ていきましょう。こちらは、寺沢知海記者による有料記事になります。これについては、無料で公開されている出だしの部分を以下に引用します。
「シェアハウスの市場が拡大している。一つの賃貸住宅に複数の人が暮らすスタイルが人気を集める背景の一つは、都市部における家賃の高騰だ。ホテル料金の値上がりもあって、訪日外国人の宿泊先としての利用も広がっている。「狭い、汚い」という従来のイメージを覆す、最新のシェアハウス事情とは。
■家賃8万6千円〜、ホテルを改築
JR浅草橋駅(東京都台東区)から徒歩5分の場所にあるビル。元々はホテルだったが、コロナ禍を機に2021年秋、2〜4階部分がシェアハウスに改築された。現在、日本人と外国人の男女18人が一緒に住む。いずれも20〜30代だ。
賃料は水道光熱費込みで8万6千円から。トイレやシャワールーム、キッチンは共用で、約4.5〜7畳の鍵付きの個室がある。入居の条件は「交流意欲」。日本人と外国人、男女の比率は半々になるように運営しているという。ダイニングテーブルやソファがある共用リビングでは、日本語と英語が飛び交い、毎週のように「たこ焼きパーティー」などが開かれる。
住人の一人で、会社員の小林正弥さん(24)は金沢市内の大学を卒業後、上京した。当初は単身向けの賃貸を探していたが、10万円ほどの家賃に加え、初期費用が30万〜50万円かかることが判明。「大学を出てすぐで、貯金もなく無理だった」。最終的にシェアハウスにたどりついた。「国際交流ができて、英語の勉強にもなる」と気に入っているという。
■23区の単身物件、とまらぬ家賃上昇
シェアハウスの魅力の一つは、アパートやマンションに比べて割安な家賃だ。(以下略)」(寺沢知海/2025年5月6日 12時00分更新)
残念ながら、無料公開部分は本題に入る前に終わり、ここから先が読みたければリンク先で購読登録する必要があります。とはいえ、登録手続きは無料ですし、登録さえすれば1ヶ月間は追加料金なしで読むことができ、読むだけ読んだ後、1ヶ月以内で退会すれば(言葉は悪いですが)「読み逃げ」することも可能です。続きが気になる方は、ぜひリンク先から登録手続きされることをおススメしておきます。
続いてご紹介するのは、東京シェアハウス合同会社が運営するシェアハウスのポータルサイト『東京シェアハウス』に4月25日付で掲載された「東京都在住の【新社会人の住居選び調査】約9割が『シェアハウス』を選択肢として検討!その実態とは?」( https://story.tokyosharehouse.com/jpn/27 )という記事。これは、2025年4月2日〜7日にかけてインターネットで実施され、東京在住の20代男女で「2025年4月から新社会人となった」191名が対象とするアンケート調査になります。以下、一部を抜粋して引用していきます。
「社会人としての新生活が始まる4月、多くの若者が直面する課題の一つが住居選びです。特に東京都内では家賃や初期費用が高騰しており、新しい住まいを探す際の悩みや不安が増えています。そんな中、『シェアハウス』は経済的負担の軽減だけでなく、人とのつながりも得られる新たな選択肢として注目されています。
(中略)
■調査結果サマリー
・新社会人の半数以上が『賃貸住宅』で暮らしている。
・約8割が、社会人になるタイミングで住居を変更している。
・住居選びで最も重視するポイントは『家賃の安さ』『間取り』『住居の立地』。
・住居選びの最大の不安は『経済的負担』『周辺環境』『契約手続きの手間』。
・約9割が住居選びの際に『シェアハウス』を選択肢として考えていた。
・シェアハウス選びでは『プライバシーの確保』を最も重要視。(後略)」
以下、グラフとともに上記のサマリー(要約)の詳細について各項目に短い解説が入りますが、それらについてはリンク先でご確認ください。ただし、最後の2項目に関してはここで少々補足しておきましょう。「約9割が〜選択肢として考えていた」の具体的な回答数の内訳は、1位「選択肢にはあったが、検討した結果、他の賃貸物件に決めた」(41.6%)、2位「有力な選択肢で、実際にシェアハウスに住むことを決めた」(40.3%)、3位「選択肢になかった」(11.0%)、4位「選択肢にはあったが、条件に合う物件がなかった」(7.1%)の順となり、この1位・2位・4位の合計89.0%について「約9割が〜」と言っているわけです。つまり、もっとも回答数の多かったのは「検討はしたが、他の賃貸物件に決めた」という回答であり、「実際にシェアハウスに決めた」という回答は(微差とはいえ)2位で、約4割に過ぎなかった……ということになります。より厳密に言えば、実際にシェアハウスに入居したのは「社会人になるタイミングで住居を変更した約8割」のうちの約4割ということですから、実数はさらに減少します。また、「『プライバシーの確保』を最も重要視」に関しては、この回答を選んだのは31.1%ですから、回答数は最多でも実態は10人中3人の割合。「家賃の安さ」を選んだ人も23.4%いましたから、10人中2人以上がこちらをより重視していたということになります。アンケート調査では、とかく集計作業を行う者の「予断」や「先入観」が先に立ち、はじめから「結論ありき」で恣意的な分析結果に陥りがちですから、ある意味「話半分」として受け止め、結果を鵜呑みにしない態度が求められます。なお、上記の記事では最後に「まとめ」として、同社からのコメントが付記されています。その中の一節を引用してみましょう。
「(前略)シェアハウスの魅力は単なる経済的なメリットだけでなく、同じ空間を共有することで生まれる人との繋がりや交流の機会にもあります。新社会人にとって『コスト削減』と『人間関係構築』の両方を実現できる住まいのスタイルとして、今後さらにニーズが高まっていくことが予想されます(後略)」
いちいちもっともな主張であり、全面的に同意したいところですが……他方では、「首都圏においては、賃貸住宅の家賃上昇傾向が今なお続いている」という厳然たる事実も見逃せません。今後、シェアハウスへのニーズがますます高まっていく、という予想は変わりませんが、その裏では、「今後はこれまで以上に、シェアハウスにコストメリットを求める入居希望者の割合が増えていく……」という、シェアハウス大家さんにとっては必ずしも歓迎できない「不都合な真実」からも目を背けてはいられないのではないでしょうか。
最後にもう1本、4月20日付『女性自身Web』に掲載された「“シニアシェアハウス”の実態とは…節約の点で注目も、共同生活でのいざこざ多発で『終の棲家にはムリ』」( https://www.jprime.jp/articles/-/36172 )という記事を見ていきましょう。以下、抜粋して引用します。
「深刻な高齢化が進む日本。その裏で問題視されているのが高齢単身者の増加だ。内閣府の令和6年版高齢社会白書によると、2025年における65歳以上の単独世帯は約800万を超え、今後も増加の一途をたどる。
■必ず住み替えが必要になる
単身シニアは孤立しやすく、1週間誰とも話さないなんてこともザラ。体調悪化の発見遅れや、孤独死などの問題も懸念されます。そこで注目されているのがシニアシェアハウス。
『入居条件は施設によって異なりますが、自立した生活を送れる介護不要のアクティブシニアであることが絶対条件。建物内に共用スペースがあり、各個室でプライバシーを保ちつつ、入居者同士で日常的に交流を楽しめるのがウリです』
と話すのは、高齢者住宅に詳しい満田将太さん。住人同士で体調の見守りもでき、物件によっては管理人がいるところも。独りではないという、安心感が心強い。
(中略)
また、住居の形態に法的な縛りがないため、空き家を利用した物件や一棟まるごとのマンションなどさまざま。
『一番の特徴は、終の棲家(すみか)にできないこと。自立して生活できることが入居の条件なので、介護が必要になると施設などへの住み替えが必要になります。
介護保険でヘルパーさんの手を借りて住み続けるケースもありますが、同居人から“プライバシーが守られない”といった不満の声があがるなど、現実的ではありません』
高齢になるほど新しい環境に移るのは大変。そのため、将来的に介護が必要になった時に、移れる施設を事前に考えておく必要がある。
(中略)
共同生活に適性がないと、トラブルに発展しやすい。実際にシェアハウス生活を送る足立一郎さん(80代前半の男性・仮名)は、同居人だった老夫婦に文句を言われたそう。
『その夫婦の奥さんのほうが、軽い認知症を患っていたのですが、ご主人が“うちの妻がこのシェアハウスで仲間外れにされている”と周囲に言い出して。私たちも奥さんに話しかけてはみたものの、うまく会話ができなかったので、様子を見ていました。疎外していたわけではないのですが……。
シェアハウスに入れば周りに気を使ってもらえて、サポートまでしてもらえる。将来的には介護まで手伝ってくれるのではないか、という思惑がこちらの夫婦にはあったようですが、私たちも他人の面倒を押しつけられても困りますし。結局、退所していきました』
(中略)
では、“向いている人”はどういう人なのだろう。
『これからどういう人生を送りたいのか、優先順位が決まっている人です。家賃が多少高くても利便性の高い都市部に住みたいのか、のんびり郊外なのか。郊外の場合は車がないと出かけられないことが多いので、そのあたりも物件選びにおいて必須になってきます』
あとは協調性に尽きるという。
『どんな人が同居しているのかは、見学しているときにチェックを。午後のお茶の時間を狙って様子を見に行くのもいいでしょう』
“元気だが独り暮らしは避けたいという高齢者”向けの住宅ニーズはますます高まるという。
『これまで賃貸物件でシニア世代は敬遠されてきましたが、少子高齢化でそうも言っていられません。最近ではシニアに特化してバリアフリー化された分譲シニアマンションなど、新たな形態のシニア住宅も生まれています。
納得のいく老後を実現するためにも、元気なうちに情報収集を始めて、自分に合った選択肢を用意したいものです』
(中略)
■満田さんに聞いたシニアシェアハウスのこぼれ話
(中略)
『日課であるラジオ体操に来なかった井上さん。管理人がおかしいと思い部屋に行ったところ、倒れていて。その後は本人も回復したので安心しましたが、やはり誰かと暮らすのは命のセーフティーネットなのだと思います』
(中略)
『シェアハウスの口コミで、SNSなどに事実無根の悪評を書かれたケースがあります。情報だけを鵜呑みにするのではなく、一度、住人に生の声を聞くなど見学を怠らないこと。逆に“口コミで評価が良いから”という理由で安易に選ぶのも後悔のモト』」
当コラムでも、これまで再三にわたって「高齢者向けシェアハウス」の話題を取り上げてきましたが、基本的には「主催者発表」に近く、多少の問題提起はあっても、マイナス面を強調するような内容は少なかったと思います。その点、上記の記事では珍しく「不都合な真実」についても遠慮なく言及しており、その意味でも参考になる貴重な情報だったのではないでしょうか。無論、女性週刊誌というメディアの特質上、ことさらセンセーショナルな強い言葉で読者の不安を煽り、売上につなげるという狙いがないとは断言できません。とはいえ、書かれている情報は(ある程度誇張されていたとしても)十分な信憑性を備えているように思われます。
今回のコラムのタイトルに使わせていただいた「不都合な真実」とは、米クリントン大統領の下で副大統領を務めていたアル・ゴア氏の脚本・主演で2006年に公開されたドキュメンタリー映画(原題:An Inconvenient Truth)および同題の著書のタイトルを拝借したものです。「地球温暖化問題」に真っ向から取り組んだこの作品自体の評価はさておき、「人間は、自分にとって都合のいい意見や事実しか見ようとせず、都合の悪い意見や事実は無視される。しかし、いくら無視しても『現実にあるものをなくす』ことはできない」という、当たり前ですが忘れられがちな真理を突いた言葉として、さまざまなジャンルで応用される一種の「流行語」となりました。シェアハウスというニッチなジャンルにおいても例外ではなく、メディアの報道や主催者発表では触れられない「不都合な真実」はいくつも存在します。何も「ひねくれたものの見方」を推奨するわけではありませんが、世の中に流通している情報の一つひとつにも「不都合な真実」が含まれている、ということを、たまには意識してみることも必要なのかもしれません。
一方、4月下旬よりカシミール地方で武力衝突が続いていたインドとパキスタンは、5月10日に停戦合意が実現したものの、今なお両国の間で緊張状態が続き、一触即発が懸念されています。世界を覆うキナ臭い空気は、まだまだ収まる様子が一向に見えてきません……。
さて、気を取り直して、今月もシェアハウス大家さんにとって気になるニュースをいくつか取り上げてみたいと思います。まずは、5月13日付の『時事通信』で報じられた「金融庁、スルガ銀に報告徴求=不正融資問題長期化で」( https://www.jiji.com/jc/article?k=2025051301284&g=eco )というニュースから。短い記事なので、以下に全文を引用します。
「スルガ銀行は13日、投資用のアパートやマンションへの不正融資問題を巡り、金融庁から銀行法に基づく報告徴求命令を受けたと発表した。金融庁は、全ての債務者の個別解決に至らず、対応が長期化していることを問題視。早期解決に向けて具体的な改善策の報告を求めた。
スルガ銀は「報告徴求を真摯に受け止め、適時適切な情報開示を行う」とコメント。相談窓口の拡充や個別対話の呼び掛けなどを通じ、解決の加速化を図る方針だ。
スルガ銀では2018年、シェアハウスなど投資用不動産を巡る不正融資が発覚。ガバナンス(企業統治)体制の強化といった再発防止策を進めるとともに、債権の一括譲渡も行い、シェアハウス問題は解決したとしている」
懐かしい――といってはさすがに語弊があるでしょうが、ひさびさに耳にする話題です。もはや固有名詞さえ記事中には見当たりませんが、言うまでもなく「かぼちゃの馬車」事件に端を発する、一連のスルガ銀不正融資問題の続報に当たります。記事中でも「シェアハウス問題は解決した」云々、というスルガ銀側の主張を取り上げていますが、当コラムでも以前、この問題については「解決した」旨の被害者の会側の見解を取り上げたことがあります。損害賠償請求を起こしていた被害者の会側の弁護士が「解決した」とコメントするのであればまだしも納得できますが、これを加害者であるスルガ銀側が口にするのは「ちょっと違うんじゃないか?」と言いたくもなります。最終的に原告が訴訟を取り下げたとしても、訴訟を起こしたという事実そのものが消滅するわけではありません。ましてや、不正融資を行ったという事実が「なかったこと」になるわけでもない。この件に限らず、日本では裁判が終わったとたん「禊(みそぎ)は済んだ」とばかりに、たちまち裁判以前の状況に逆戻りしてしまう事例がしばしばあります。その意味で、金融庁の今回の対応は「理に適った」ものだということができますし、「やらかしてしまった側」であるスルガ銀が「問題は解決した」などと主張するのは、いささか事実認識が甘い、と言わざるを得ないでしょう。
続いて、『朝日新聞デジタル』が5月6日付で報道した「シェアハウス人気、家賃高騰が背景 ホテル代わりに使う訪日外国人も」( https://www.asahi.com/articles/AST521W23T52OXIE046M.html )という記事を見ていきましょう。こちらは、寺沢知海記者による有料記事になります。これについては、無料で公開されている出だしの部分を以下に引用します。
「シェアハウスの市場が拡大している。一つの賃貸住宅に複数の人が暮らすスタイルが人気を集める背景の一つは、都市部における家賃の高騰だ。ホテル料金の値上がりもあって、訪日外国人の宿泊先としての利用も広がっている。「狭い、汚い」という従来のイメージを覆す、最新のシェアハウス事情とは。
■家賃8万6千円〜、ホテルを改築
JR浅草橋駅(東京都台東区)から徒歩5分の場所にあるビル。元々はホテルだったが、コロナ禍を機に2021年秋、2〜4階部分がシェアハウスに改築された。現在、日本人と外国人の男女18人が一緒に住む。いずれも20〜30代だ。
賃料は水道光熱費込みで8万6千円から。トイレやシャワールーム、キッチンは共用で、約4.5〜7畳の鍵付きの個室がある。入居の条件は「交流意欲」。日本人と外国人、男女の比率は半々になるように運営しているという。ダイニングテーブルやソファがある共用リビングでは、日本語と英語が飛び交い、毎週のように「たこ焼きパーティー」などが開かれる。
住人の一人で、会社員の小林正弥さん(24)は金沢市内の大学を卒業後、上京した。当初は単身向けの賃貸を探していたが、10万円ほどの家賃に加え、初期費用が30万〜50万円かかることが判明。「大学を出てすぐで、貯金もなく無理だった」。最終的にシェアハウスにたどりついた。「国際交流ができて、英語の勉強にもなる」と気に入っているという。
■23区の単身物件、とまらぬ家賃上昇
シェアハウスの魅力の一つは、アパートやマンションに比べて割安な家賃だ。(以下略)」(寺沢知海/2025年5月6日 12時00分更新)
残念ながら、無料公開部分は本題に入る前に終わり、ここから先が読みたければリンク先で購読登録する必要があります。とはいえ、登録手続きは無料ですし、登録さえすれば1ヶ月間は追加料金なしで読むことができ、読むだけ読んだ後、1ヶ月以内で退会すれば(言葉は悪いですが)「読み逃げ」することも可能です。続きが気になる方は、ぜひリンク先から登録手続きされることをおススメしておきます。
続いてご紹介するのは、東京シェアハウス合同会社が運営するシェアハウスのポータルサイト『東京シェアハウス』に4月25日付で掲載された「東京都在住の【新社会人の住居選び調査】約9割が『シェアハウス』を選択肢として検討!その実態とは?」( https://story.tokyosharehouse.com/jpn/27 )という記事。これは、2025年4月2日〜7日にかけてインターネットで実施され、東京在住の20代男女で「2025年4月から新社会人となった」191名が対象とするアンケート調査になります。以下、一部を抜粋して引用していきます。
「社会人としての新生活が始まる4月、多くの若者が直面する課題の一つが住居選びです。特に東京都内では家賃や初期費用が高騰しており、新しい住まいを探す際の悩みや不安が増えています。そんな中、『シェアハウス』は経済的負担の軽減だけでなく、人とのつながりも得られる新たな選択肢として注目されています。
(中略)
■調査結果サマリー
・新社会人の半数以上が『賃貸住宅』で暮らしている。
・約8割が、社会人になるタイミングで住居を変更している。
・住居選びで最も重視するポイントは『家賃の安さ』『間取り』『住居の立地』。
・住居選びの最大の不安は『経済的負担』『周辺環境』『契約手続きの手間』。
・約9割が住居選びの際に『シェアハウス』を選択肢として考えていた。
・シェアハウス選びでは『プライバシーの確保』を最も重要視。(後略)」
以下、グラフとともに上記のサマリー(要約)の詳細について各項目に短い解説が入りますが、それらについてはリンク先でご確認ください。ただし、最後の2項目に関してはここで少々補足しておきましょう。「約9割が〜選択肢として考えていた」の具体的な回答数の内訳は、1位「選択肢にはあったが、検討した結果、他の賃貸物件に決めた」(41.6%)、2位「有力な選択肢で、実際にシェアハウスに住むことを決めた」(40.3%)、3位「選択肢になかった」(11.0%)、4位「選択肢にはあったが、条件に合う物件がなかった」(7.1%)の順となり、この1位・2位・4位の合計89.0%について「約9割が〜」と言っているわけです。つまり、もっとも回答数の多かったのは「検討はしたが、他の賃貸物件に決めた」という回答であり、「実際にシェアハウスに決めた」という回答は(微差とはいえ)2位で、約4割に過ぎなかった……ということになります。より厳密に言えば、実際にシェアハウスに入居したのは「社会人になるタイミングで住居を変更した約8割」のうちの約4割ということですから、実数はさらに減少します。また、「『プライバシーの確保』を最も重要視」に関しては、この回答を選んだのは31.1%ですから、回答数は最多でも実態は10人中3人の割合。「家賃の安さ」を選んだ人も23.4%いましたから、10人中2人以上がこちらをより重視していたということになります。アンケート調査では、とかく集計作業を行う者の「予断」や「先入観」が先に立ち、はじめから「結論ありき」で恣意的な分析結果に陥りがちですから、ある意味「話半分」として受け止め、結果を鵜呑みにしない態度が求められます。なお、上記の記事では最後に「まとめ」として、同社からのコメントが付記されています。その中の一節を引用してみましょう。
「(前略)シェアハウスの魅力は単なる経済的なメリットだけでなく、同じ空間を共有することで生まれる人との繋がりや交流の機会にもあります。新社会人にとって『コスト削減』と『人間関係構築』の両方を実現できる住まいのスタイルとして、今後さらにニーズが高まっていくことが予想されます(後略)」
いちいちもっともな主張であり、全面的に同意したいところですが……他方では、「首都圏においては、賃貸住宅の家賃上昇傾向が今なお続いている」という厳然たる事実も見逃せません。今後、シェアハウスへのニーズがますます高まっていく、という予想は変わりませんが、その裏では、「今後はこれまで以上に、シェアハウスにコストメリットを求める入居希望者の割合が増えていく……」という、シェアハウス大家さんにとっては必ずしも歓迎できない「不都合な真実」からも目を背けてはいられないのではないでしょうか。
最後にもう1本、4月20日付『女性自身Web』に掲載された「“シニアシェアハウス”の実態とは…節約の点で注目も、共同生活でのいざこざ多発で『終の棲家にはムリ』」( https://www.jprime.jp/articles/-/36172 )という記事を見ていきましょう。以下、抜粋して引用します。
「深刻な高齢化が進む日本。その裏で問題視されているのが高齢単身者の増加だ。内閣府の令和6年版高齢社会白書によると、2025年における65歳以上の単独世帯は約800万を超え、今後も増加の一途をたどる。
■必ず住み替えが必要になる
単身シニアは孤立しやすく、1週間誰とも話さないなんてこともザラ。体調悪化の発見遅れや、孤独死などの問題も懸念されます。そこで注目されているのがシニアシェアハウス。
『入居条件は施設によって異なりますが、自立した生活を送れる介護不要のアクティブシニアであることが絶対条件。建物内に共用スペースがあり、各個室でプライバシーを保ちつつ、入居者同士で日常的に交流を楽しめるのがウリです』
と話すのは、高齢者住宅に詳しい満田将太さん。住人同士で体調の見守りもでき、物件によっては管理人がいるところも。独りではないという、安心感が心強い。
(中略)
また、住居の形態に法的な縛りがないため、空き家を利用した物件や一棟まるごとのマンションなどさまざま。
『一番の特徴は、終の棲家(すみか)にできないこと。自立して生活できることが入居の条件なので、介護が必要になると施設などへの住み替えが必要になります。
介護保険でヘルパーさんの手を借りて住み続けるケースもありますが、同居人から“プライバシーが守られない”といった不満の声があがるなど、現実的ではありません』
高齢になるほど新しい環境に移るのは大変。そのため、将来的に介護が必要になった時に、移れる施設を事前に考えておく必要がある。
(中略)
共同生活に適性がないと、トラブルに発展しやすい。実際にシェアハウス生活を送る足立一郎さん(80代前半の男性・仮名)は、同居人だった老夫婦に文句を言われたそう。
『その夫婦の奥さんのほうが、軽い認知症を患っていたのですが、ご主人が“うちの妻がこのシェアハウスで仲間外れにされている”と周囲に言い出して。私たちも奥さんに話しかけてはみたものの、うまく会話ができなかったので、様子を見ていました。疎外していたわけではないのですが……。
シェアハウスに入れば周りに気を使ってもらえて、サポートまでしてもらえる。将来的には介護まで手伝ってくれるのではないか、という思惑がこちらの夫婦にはあったようですが、私たちも他人の面倒を押しつけられても困りますし。結局、退所していきました』
(中略)
では、“向いている人”はどういう人なのだろう。
『これからどういう人生を送りたいのか、優先順位が決まっている人です。家賃が多少高くても利便性の高い都市部に住みたいのか、のんびり郊外なのか。郊外の場合は車がないと出かけられないことが多いので、そのあたりも物件選びにおいて必須になってきます』
あとは協調性に尽きるという。
『どんな人が同居しているのかは、見学しているときにチェックを。午後のお茶の時間を狙って様子を見に行くのもいいでしょう』
“元気だが独り暮らしは避けたいという高齢者”向けの住宅ニーズはますます高まるという。
『これまで賃貸物件でシニア世代は敬遠されてきましたが、少子高齢化でそうも言っていられません。最近ではシニアに特化してバリアフリー化された分譲シニアマンションなど、新たな形態のシニア住宅も生まれています。
納得のいく老後を実現するためにも、元気なうちに情報収集を始めて、自分に合った選択肢を用意したいものです』
(中略)
■満田さんに聞いたシニアシェアハウスのこぼれ話
(中略)
『日課であるラジオ体操に来なかった井上さん。管理人がおかしいと思い部屋に行ったところ、倒れていて。その後は本人も回復したので安心しましたが、やはり誰かと暮らすのは命のセーフティーネットなのだと思います』
(中略)
『シェアハウスの口コミで、SNSなどに事実無根の悪評を書かれたケースがあります。情報だけを鵜呑みにするのではなく、一度、住人に生の声を聞くなど見学を怠らないこと。逆に“口コミで評価が良いから”という理由で安易に選ぶのも後悔のモト』」
当コラムでも、これまで再三にわたって「高齢者向けシェアハウス」の話題を取り上げてきましたが、基本的には「主催者発表」に近く、多少の問題提起はあっても、マイナス面を強調するような内容は少なかったと思います。その点、上記の記事では珍しく「不都合な真実」についても遠慮なく言及しており、その意味でも参考になる貴重な情報だったのではないでしょうか。無論、女性週刊誌というメディアの特質上、ことさらセンセーショナルな強い言葉で読者の不安を煽り、売上につなげるという狙いがないとは断言できません。とはいえ、書かれている情報は(ある程度誇張されていたとしても)十分な信憑性を備えているように思われます。
今回のコラムのタイトルに使わせていただいた「不都合な真実」とは、米クリントン大統領の下で副大統領を務めていたアル・ゴア氏の脚本・主演で2006年に公開されたドキュメンタリー映画(原題:An Inconvenient Truth)および同題の著書のタイトルを拝借したものです。「地球温暖化問題」に真っ向から取り組んだこの作品自体の評価はさておき、「人間は、自分にとって都合のいい意見や事実しか見ようとせず、都合の悪い意見や事実は無視される。しかし、いくら無視しても『現実にあるものをなくす』ことはできない」という、当たり前ですが忘れられがちな真理を突いた言葉として、さまざまなジャンルで応用される一種の「流行語」となりました。シェアハウスというニッチなジャンルにおいても例外ではなく、メディアの報道や主催者発表では触れられない「不都合な真実」はいくつも存在します。何も「ひねくれたものの見方」を推奨するわけではありませんが、世の中に流通している情報の一つひとつにも「不都合な真実」が含まれている、ということを、たまには意識してみることも必要なのかもしれません。
|
第137回 変わらぬ魅力とシェアハウス |
新・今月の不動産コラム |
第135回 時の流れとシェアハウス |
シェアハウス大家さん倶楽部について
新着コンテンツ
-
第144回 2026年とシェアハウス
2026-1-15 -
第143回 変化の時代とシェアハウス
2025-12-19 -
第142回 光明とシェアハウス
2025-11-17 -
第141回 抵抗感とシェアハウス
2025-10-16 -
第140回 未来予想図とシェアハウス
2025-9-16 -
第139回 不動産市況とシェアハウス2025夏
2025-8-16 -
第138回 公的支援とシェアハウス
2025-7-15 -
第137回 変わらぬ魅力とシェアハウス
2025-6-16 -
第136回 「不都合な真実」とシェアハウス
2025-5-16 -
第135回 時の流れとシェアハウス
2025-4-17
〜シェアハウス事業を企画から運営まで、トータルにサポート〜
運営会社:株式会社シェアスタイル | シェアハウス資産運用のご相談はこちら | シェアハウス管理物件のご紹介はこちら | 採用情報
Copyright © 2006-2015 ShareStyle Co.,Ltd. All Rights Reserved.