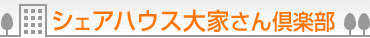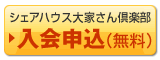第26話 ヤマダくん、一件落着?
「……やれやれ、だな」
ホッと息をつきながらヤマダくんがそう言うと、
「ホント、やれやれ、ね……」
ワタナベさんも調子を合わせる。ちょっと前までのトゲトゲしい雰囲気はなくなり、どことなく甘えた口調になっていた。
ふり返れば、嵐のような数週間だった。しかし、今やヤマダくんのシェアハウス『バーデン-H』に立ち込めていた重苦しい空気は一掃され、もとの明るいハウスに立ち返ったように感じられた。
――オーストラリアはメルボルンからやってきた金髪グラマー、メアリー・ワトキンス嬢は、当初の予定より2週間ほど遅れて、年が明けた1月の3連休最終日に帰国したばかりだった。年内いっぱいという予定であったときにも、すでに限界に近いくらいのピリピリしていたハウス内の空気は、しかし、帰国の前後には誰もが名残りを惜しむような雰囲気へと一変していた。1月11日の土曜日に行われた送別パーティでは、むしろサバサバした態度をとっているメアリーに対して、他の女性陣が涙を浮かべるシーンもあったほどだ。
そして、そのしんみりムードは、メアリーが帰国して2週間近い今も、ワタナベさんや他のシェアメイトたちにもまだかすかに残っている感じだった。
「……また、来てくれる……よね?」
そんなふうにメアリーの存在を懐かしがっているワタナベさんを見ながら、ヤマダくんは、あの、ギスギスした昨年暮れの雰囲気が180度変わった、クリスマスパーティのことを思い出すのだった。
ヤマダくんたちが『バーデン-H』を開設して、2回目のクリスマス――。
思い起こせば、1回目の前年は最悪だった。
当時、205号室に入居していたヨシザワさんという女性が、クリスマス直前にいきなり退去を申し出てきた。オープン以来、初めての退去者だった。その影響で、予定していたクリスマスパーティはお流れになり、さらにそれ以後、ハウス主催の月例パーティが長らく中断するきっかけにもなった。
昨秋、アオノさんたちの加入でようやく月例パーティは復活したものの、メアリーと他の女性入居者たちとの間が気まずくなり、このぶんだと2回目のクリスマスまでお流れになりかねない――そんなふうにヤマダくんが思っていたときだった。
「やろうよ、パーティ」
そう、きっぱり言い切ったのはアオノさんだった。
「そりゃ、やりたいけど……」
1年前の苦い記憶のせいか、ヤマダくんはイマイチふんぎりがつかないようすだ。
「『やりたい』ならやるんだよ。悩んだって仕方がない」
何か思いついたらしく、アオノさんの口調に迷いはなかった。
――12月は会社の繁忙期で時間の取りにくいヤマダくんとワタナベさんに代わって、アオノさんが彼女のフジノさんとふたりで幹事を務めることになり、クリスマスパーティの企画は着々と進行していった。ふたりの入念な根回しのおかげで不参加を表明する者もなく、ドタキャンもない、文字通り全員参加で無事、パーティ当日を迎えることができた。
その当日――アオノさんは唐突に、テーブルを囲んだシェアメイトたちに向かって、こんなことを言い出した。
「えー、今年のクリスマスパーティですが、ちょっとばかり変わった趣向で行いたいと思います」
「………………?」
一同が怪訝そうに見守るなか、アオノさんはニヤリと笑って続ける。
「こうして、皆さんに持ちよっていただいた食材を……」
言いながら、アオノさんはエビフライや鶏のから揚げ、フライドポテトやミニトマトなどが盛られたオードブルの皿をひょいと取り上げ、中央の巨大な鍋の中へ、ざーっと皿の中身をぶちまけた!
「え――!?」
シェアメイトたちがいっせいにどよめく。
が、アオノさんとフジノさんは、フライドチキンやシーザーサラダ、ポテトサラダ、ハムやソーセージ、フルーツの盛り合わせなど、テーブルに所狭しと並べられた皿を次々に手に取り、片っぱしから鍋の中に流し込んでいく。
「ちょ……あの!」
「何を……?」
「そんな……」
驚き慌てるシェアメイトたちをよそに、あらかた大鍋に食材を投入すると、アオノさんはガスコンロの火を点けた。そして、おもむろに立ち上がったヤマダくんに合図すると、ヤマダくんはリビングの照明を落とした。
コンロの青白い炎だけを残して、リビングは闇に閉ざされた。
「……ご静粛に!」
ヤマダくんは一同にそう声をかけてから、鍋の前のアオノさんに振る。コンロの炎に下から照らされたアオノさんが、厳かに宣言した。
「日本古来の伝統に則り、今夜はひとつ、闇鍋パーティと洒落こみたいと思います」
――闇鍋。
それが、アオノさんが思いついたという起死回生のアイデアだった。
一種のサプライズだが、事前の根回しで持ち寄ってもらう食材については「味、匂いがきょくたんにキツい物」「殻が固いなど、食べるのに手間のかかる物」など、鍋に入れるのに向かない食材は避けている。その際、ある程度趣向のことも匂わせておいたから、察しの良いメンバーならあらかじめ予想がついていたはずだ。
そういう意味では、もっとも純粋に驚いているのがメアリーだった。
「Yaminabe……What?」
しきりに「?」マークを連発するメアリーに、周囲に座っているシェアメイトたちが口々に説明する。
「こう、真っ暗にしてね、順番に鍋にハシをつけていくの」
「一度ハシで触った食べ物は、ぜったい食べなきゃいけないのよ!」
「だいじょうぶ、さっき見たでしょ? 基本的に食べられないものは入ってないから」
「ただ、暗いから、口に入れるまでそれが何なのかはわからないの。そこがおもしろいんだけどね」
闇に包まれているという安心感もあってか、いつしか女性陣のメアリーに対するわだかまりも薄らいできたようだった。
おっかなびっくり、闇鍋パーティは進んでいく。やがて――ひさびさに、『バーデン-H』のリビングのそこここで屈託のない笑い声が聞こえはじめていた。
(つづく)
ホッと息をつきながらヤマダくんがそう言うと、
「ホント、やれやれ、ね……」
ワタナベさんも調子を合わせる。ちょっと前までのトゲトゲしい雰囲気はなくなり、どことなく甘えた口調になっていた。
ふり返れば、嵐のような数週間だった。しかし、今やヤマダくんのシェアハウス『バーデン-H』に立ち込めていた重苦しい空気は一掃され、もとの明るいハウスに立ち返ったように感じられた。
――オーストラリアはメルボルンからやってきた金髪グラマー、メアリー・ワトキンス嬢は、当初の予定より2週間ほど遅れて、年が明けた1月の3連休最終日に帰国したばかりだった。年内いっぱいという予定であったときにも、すでに限界に近いくらいのピリピリしていたハウス内の空気は、しかし、帰国の前後には誰もが名残りを惜しむような雰囲気へと一変していた。1月11日の土曜日に行われた送別パーティでは、むしろサバサバした態度をとっているメアリーに対して、他の女性陣が涙を浮かべるシーンもあったほどだ。
そして、そのしんみりムードは、メアリーが帰国して2週間近い今も、ワタナベさんや他のシェアメイトたちにもまだかすかに残っている感じだった。
「……また、来てくれる……よね?」
そんなふうにメアリーの存在を懐かしがっているワタナベさんを見ながら、ヤマダくんは、あの、ギスギスした昨年暮れの雰囲気が180度変わった、クリスマスパーティのことを思い出すのだった。
ヤマダくんたちが『バーデン-H』を開設して、2回目のクリスマス――。
思い起こせば、1回目の前年は最悪だった。
当時、205号室に入居していたヨシザワさんという女性が、クリスマス直前にいきなり退去を申し出てきた。オープン以来、初めての退去者だった。その影響で、予定していたクリスマスパーティはお流れになり、さらにそれ以後、ハウス主催の月例パーティが長らく中断するきっかけにもなった。
昨秋、アオノさんたちの加入でようやく月例パーティは復活したものの、メアリーと他の女性入居者たちとの間が気まずくなり、このぶんだと2回目のクリスマスまでお流れになりかねない――そんなふうにヤマダくんが思っていたときだった。
「やろうよ、パーティ」
そう、きっぱり言い切ったのはアオノさんだった。
「そりゃ、やりたいけど……」
1年前の苦い記憶のせいか、ヤマダくんはイマイチふんぎりがつかないようすだ。
「『やりたい』ならやるんだよ。悩んだって仕方がない」
何か思いついたらしく、アオノさんの口調に迷いはなかった。
――12月は会社の繁忙期で時間の取りにくいヤマダくんとワタナベさんに代わって、アオノさんが彼女のフジノさんとふたりで幹事を務めることになり、クリスマスパーティの企画は着々と進行していった。ふたりの入念な根回しのおかげで不参加を表明する者もなく、ドタキャンもない、文字通り全員参加で無事、パーティ当日を迎えることができた。
その当日――アオノさんは唐突に、テーブルを囲んだシェアメイトたちに向かって、こんなことを言い出した。
「えー、今年のクリスマスパーティですが、ちょっとばかり変わった趣向で行いたいと思います」
「………………?」
一同が怪訝そうに見守るなか、アオノさんはニヤリと笑って続ける。
「こうして、皆さんに持ちよっていただいた食材を……」
言いながら、アオノさんはエビフライや鶏のから揚げ、フライドポテトやミニトマトなどが盛られたオードブルの皿をひょいと取り上げ、中央の巨大な鍋の中へ、ざーっと皿の中身をぶちまけた!
「え――!?」
シェアメイトたちがいっせいにどよめく。
が、アオノさんとフジノさんは、フライドチキンやシーザーサラダ、ポテトサラダ、ハムやソーセージ、フルーツの盛り合わせなど、テーブルに所狭しと並べられた皿を次々に手に取り、片っぱしから鍋の中に流し込んでいく。
「ちょ……あの!」
「何を……?」
「そんな……」
驚き慌てるシェアメイトたちをよそに、あらかた大鍋に食材を投入すると、アオノさんはガスコンロの火を点けた。そして、おもむろに立ち上がったヤマダくんに合図すると、ヤマダくんはリビングの照明を落とした。
コンロの青白い炎だけを残して、リビングは闇に閉ざされた。
「……ご静粛に!」
ヤマダくんは一同にそう声をかけてから、鍋の前のアオノさんに振る。コンロの炎に下から照らされたアオノさんが、厳かに宣言した。
「日本古来の伝統に則り、今夜はひとつ、闇鍋パーティと洒落こみたいと思います」
――闇鍋。
それが、アオノさんが思いついたという起死回生のアイデアだった。
一種のサプライズだが、事前の根回しで持ち寄ってもらう食材については「味、匂いがきょくたんにキツい物」「殻が固いなど、食べるのに手間のかかる物」など、鍋に入れるのに向かない食材は避けている。その際、ある程度趣向のことも匂わせておいたから、察しの良いメンバーならあらかじめ予想がついていたはずだ。
そういう意味では、もっとも純粋に驚いているのがメアリーだった。
「Yaminabe……What?」
しきりに「?」マークを連発するメアリーに、周囲に座っているシェアメイトたちが口々に説明する。
「こう、真っ暗にしてね、順番に鍋にハシをつけていくの」
「一度ハシで触った食べ物は、ぜったい食べなきゃいけないのよ!」
「だいじょうぶ、さっき見たでしょ? 基本的に食べられないものは入ってないから」
「ただ、暗いから、口に入れるまでそれが何なのかはわからないの。そこがおもしろいんだけどね」
闇に包まれているという安心感もあってか、いつしか女性陣のメアリーに対するわだかまりも薄らいできたようだった。
おっかなびっくり、闇鍋パーティは進んでいく。やがて――ひさびさに、『バーデン-H』のリビングのそこここで屈託のない笑い声が聞こえはじめていた。
(つづく)
シェアハウス大家さん倶楽部について
新着コンテンツ
-
第123回 ライフステージとシェアハウス
2024-4-16 -
第122回 景気回復とシェアハウス2024
2024-3-15 -
第121回 生活困窮者とシェアハウス
2024-2-15 -
第120回 震災とシェアハウス2024
2024-1-15 -
第119回 プレスリリースとシェアハウスその2
2023-12-15 -
第118回 住宅難とシェアハウス
2023-11-30 -
第117回 プレスリリースとシェアハウス
2023-10-15 -
第116回 アンケート調査とシェアハウス
2023-9-15 -
第115回 防災とシェアハウス
2023-8-15 -
第114回 猛暑とシェアハウス
2023-7-15
〜シェアハウス事業を企画から運営まで、トータルにサポート〜
運営会社:株式会社シェアスタイル | シェアハウス資産運用のご相談はこちら | シェアハウス管理物件のご紹介はこちら | 採用情報
Copyright © 2006-2015 ShareStyle Co.,Ltd. All Rights Reserved.