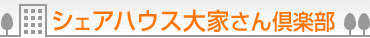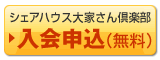第53話 ヤマダくん、倒れる!?
ピピピピッ、ピピピピッ……と軽やかな電子音が鳴った。
ぼんやりした意識の中で、ヤマダくんはのろのろと手を布団から出し、咥えた体温計を口から抜くとデジタル表示を確認した。
――38.6℃。
前夜、寝る前に測ったときには39.2℃だったから、いくらかマシになったとはいえ、「下がった」とはとうてい言えない高熱である。あと1日――ことによったらもう2、3日はようすを見たほうがいいかもしれない。
(……もしかして、インフル? ………まさかなぁ……)
可能性はある。というか、ふつうの風邪でここまで熱が出たことは記憶になかった。これはどうやら、病院でちゃんと検査を受ける必要がありそうだ。
――何日か前から、なんとなく身体がだるいとは感じていたヤマダくんだった。昨日の朝からは、咳も出るようになっていた。だが、空気が乾燥しているせいだろうとさして気にも留めず、そのまま会社で仕事を続けていたのだが――夜ハウスに帰り着いたとたん、ヤマダくんは、自分が立っていられないほどの状態であることに気づいたのである。
幸い、その場でぶっ倒れるようなことはなかったものの、玄関から自室である101号室まで移動するには、ちょうどリビングにいた102号室のイトウくんの肩を借りなければならなかった。どうにかベッドまでたどり着くと、今度は婚約者のワタナベさんの手を借りてどうにか着替え、布団にもぐり込んだ。朦朧とした意識の中で、ワタナベさんが部屋から持ってきた体温計を咥えさせられたところまではかろうじて覚えていた。
「インフルエンザの流行に備えて、前もって予防接種しておくくらいのことは、集団生活の上で当然のマナーだ……」というのがヤマダくんの個人的な考えではあったが――さすがに入居者全員に予防接種を義務づけることまではしていない。せいぜい、洗面所にうがい・手洗いを励行する貼り紙をしたり、リビングなどで顔を合わせたときに個別に「予防接種、しといた方がいいよ」などと注意を促すくらいが関の山だ。それどころか、そもそもヤマダくん自身が昨秋は職場の繁忙期にかこつけて予防接種を受けていなかったのだから、他人のことをどうのこうの言えた義理ではないのだが……。
と――ドアに、控えめなノックの音がした。
「入っていい……?」
一応、そう問いかけはしたものの、返事を待つこともなく――ガチャガチャ音がしたかと思うと、101号室のドアがいきなり開かれた。咽喉が腫れあがり、とっさに声も出せなくなっていたヤマダくんは、無言で入り口の方へ目を向けるしかできなかった。
『バーデン-H』の各個室は一応、プライバシーを配慮してカギをかけられるようにつくられている。明け方、トイレに立ったヤマダくんが部屋に戻ったときにも、習慣的に施錠したような気がする。施錠されたドアを外から開けられるのは、マスターキーを持っている人間だけ。そんな人間はヤマダくんの知る限りひとりしかいない。――いうまでもなく、ヤマダくんの婚約者であり、ハウスの共同経営者でもあるワタナベさんであった。
「……どうなの、具合は?」
ワタナベさんは、開いたドアの隙間から身を滑り込ませるように入室してきた。伝染らないようにとの用心のためか、顔の下半分を白いマスクで覆っている。
「んー………」
苦しい息の中で、ヤマダくんはかろうじてまだ熱が下がらないことを伝える。枕元に置かれた体温計をチラリと一瞥して、ワタナベさんは言った。
「今日は会社休んで、病院へもちゃんと行ってくるのよ。インフルエンザの検査も受けて、陽性だったらしっかり休まないと……」
「うん……」
「それと、会社に電話も。自分でできるよね……?」
「ん……」
ヤマダくんとワタナベさんとは同じ会社に勤めているが、部署が違う。欠勤する場合には、同じ部署の人間に申し送りをしなければならない案件もあった。それに、会社の中には、婚約どころか、ふたりがつきあっている事実さえ未だに知らない人間もいるから、仮にも独身女性であるワタナベさんに伝言を頼むわけにはいかなかったのである。
「……じゃ、そろそろ会社に行ってくるから。何か欲しい物、ある?」
「…………」
ヤマダくんは無言で首を振った。声を出すのも億劫だったのだ。
「なるべく早く帰ってくるから。……無理しないでね」
手を振って、ワタナベさんがドアの向こうへ顔を引っ込める。バタン、とドアが閉められた。キッチンや洗面所、あるいは玄関の方から、シェアメイトたちが朝の支度を整え、三々五々出勤していく物音が伝わってきた。各自の出勤時間は人それぞれだが、『バーデン-H』では入居時の面接で基本的に昼勤者に限定している。生活時間のきょくたんに違う入居者がいると、共同生活の上で何かと不都合が生じるからだ。ベッドの中で耳にする出勤時間帯の喧騒は、何となく新鮮なものに感じられた。
ベッドサイドの時計に目をやると、7時40分――会社に電話するにはまだ早すぎる。
(……もうひと眠りするか)
そう考えて、ヤマダくんはふたたび瞼を閉じた。
……ふいに、鼻腔をくすぐる匂いを感じた。空っぽの胃袋を刺激する、食べ物の匂いだった。ヤマダくんがかすかに身じろぎすると、匂いのする方から声がかけられた。
「……あ。起こしちゃいましたぁ?」
甘ったるく語尾を伸ばす、独特のアニメ声だ。
「んー…………?」
半分寝ぼけたまま、ヤマダくんが音程だけで質問をぶつける。「どうした? 何故、この部屋にいるんだ?」というニュアンスの問いかけだった。
「えっと、お腹が空いてるんじゃないかと思ってぇ……」
当たり前のようにそう答えながら、声の主――202号室のマナセさんは手にしたお盆を見せた。お盆の上では、一人用の土鍋がぐつぐつと音を立てている。
「お粥ですぅ。冷めないうちにどうぞぉ……」
にっこりとお盆を差し出してみせるマナセさんに、ヤマダくんはベッドの中でいささか困惑していた。
もちろん、恋人でもない彼女にこんなことをしてもらう理由はない。だが、この場はひとまず受け取らないことにはどうにも収まらないような雰囲気だった。狙ってやっているなら大したタマだが、おそらくは天然なのだろう。
ヤマダくんは意を決して、ベッドに上体を起こすと、土鍋のお盆を受け取った。それから、マナセさんの目を正面から見て、ゆっくりと言い聞かせることにした。
――ありがとう。その気遣いはとてもうれしい。でも、こんなことをしてはいけない。もし、こういうことをする場合は、相手と特別な関係にあるか、一対一ではないときだけにしなさい……。
痛む咽喉で、発声に苦労しながら、ヤマダくんは諄々と説いた。
――キミは純粋な厚意でやってくれているんだろうけど、相手も誤解するし、周囲も誤解する。特に、こういう集団生活の場では、つまらん誤解で人間関係がギクシャクしてくるのがいちばん怖いんだ……。
しかし――。
「えー、でもぉ……」
マナセさんは唇を尖らせると、拗ねたようにこう言ってのけた。
「誤解とかぁ、そういうんじゃなくてぇ……」
「……」
「わたしはぁ……ヤマダさんのこと、好きですよ?」
「………?」
「ヤマダさんとぉ……特別な関係……に、なりたいと、思ってますよ?」
「……………ッ!?」
そのとき――。
遅まきながら、本当に遅まきながら――ヤマダくんはものすごく根本的なことに気づいたのである。
(この娘は……おれとワタナベさんのことを……気づいてなかったのか!?)
たしかに、ことさら改まってふたりの関係を説明したりはしなかったが――「それぐらい、見てりゃわかるだろう? いちいち言わせんな。察しろよ」というのがヤマダくんの本音であった。それがどうやら、マナセさんにはまったく伝わっていなかったらしいのだ。なんだかんだで、半年近くもひとつ屋根の下で暮らしているにもかかわらず……。
(やれやれ……これはいったい、どこから説明したものか……?)
ここまでくると「天然」だの「空気が読めない」だのというレベルではない。ヤマダくんも詳しくは知らないが、「アスペルガー症候群」とやらを疑ってみる必要もありそうだ。
ともあれ、問題点ははっきりした。ただし――ある意味、そのためにかえって厄介なことになったという気がしないでもない、ヤマダくんであった。
(つづく)
ぼんやりした意識の中で、ヤマダくんはのろのろと手を布団から出し、咥えた体温計を口から抜くとデジタル表示を確認した。
――38.6℃。
前夜、寝る前に測ったときには39.2℃だったから、いくらかマシになったとはいえ、「下がった」とはとうてい言えない高熱である。あと1日――ことによったらもう2、3日はようすを見たほうがいいかもしれない。
(……もしかして、インフル? ………まさかなぁ……)
可能性はある。というか、ふつうの風邪でここまで熱が出たことは記憶になかった。これはどうやら、病院でちゃんと検査を受ける必要がありそうだ。
――何日か前から、なんとなく身体がだるいとは感じていたヤマダくんだった。昨日の朝からは、咳も出るようになっていた。だが、空気が乾燥しているせいだろうとさして気にも留めず、そのまま会社で仕事を続けていたのだが――夜ハウスに帰り着いたとたん、ヤマダくんは、自分が立っていられないほどの状態であることに気づいたのである。
幸い、その場でぶっ倒れるようなことはなかったものの、玄関から自室である101号室まで移動するには、ちょうどリビングにいた102号室のイトウくんの肩を借りなければならなかった。どうにかベッドまでたどり着くと、今度は婚約者のワタナベさんの手を借りてどうにか着替え、布団にもぐり込んだ。朦朧とした意識の中で、ワタナベさんが部屋から持ってきた体温計を咥えさせられたところまではかろうじて覚えていた。
「インフルエンザの流行に備えて、前もって予防接種しておくくらいのことは、集団生活の上で当然のマナーだ……」というのがヤマダくんの個人的な考えではあったが――さすがに入居者全員に予防接種を義務づけることまではしていない。せいぜい、洗面所にうがい・手洗いを励行する貼り紙をしたり、リビングなどで顔を合わせたときに個別に「予防接種、しといた方がいいよ」などと注意を促すくらいが関の山だ。それどころか、そもそもヤマダくん自身が昨秋は職場の繁忙期にかこつけて予防接種を受けていなかったのだから、他人のことをどうのこうの言えた義理ではないのだが……。
と――ドアに、控えめなノックの音がした。
「入っていい……?」
一応、そう問いかけはしたものの、返事を待つこともなく――ガチャガチャ音がしたかと思うと、101号室のドアがいきなり開かれた。咽喉が腫れあがり、とっさに声も出せなくなっていたヤマダくんは、無言で入り口の方へ目を向けるしかできなかった。
『バーデン-H』の各個室は一応、プライバシーを配慮してカギをかけられるようにつくられている。明け方、トイレに立ったヤマダくんが部屋に戻ったときにも、習慣的に施錠したような気がする。施錠されたドアを外から開けられるのは、マスターキーを持っている人間だけ。そんな人間はヤマダくんの知る限りひとりしかいない。――いうまでもなく、ヤマダくんの婚約者であり、ハウスの共同経営者でもあるワタナベさんであった。
「……どうなの、具合は?」
ワタナベさんは、開いたドアの隙間から身を滑り込ませるように入室してきた。伝染らないようにとの用心のためか、顔の下半分を白いマスクで覆っている。
「んー………」
苦しい息の中で、ヤマダくんはかろうじてまだ熱が下がらないことを伝える。枕元に置かれた体温計をチラリと一瞥して、ワタナベさんは言った。
「今日は会社休んで、病院へもちゃんと行ってくるのよ。インフルエンザの検査も受けて、陽性だったらしっかり休まないと……」
「うん……」
「それと、会社に電話も。自分でできるよね……?」
「ん……」
ヤマダくんとワタナベさんとは同じ会社に勤めているが、部署が違う。欠勤する場合には、同じ部署の人間に申し送りをしなければならない案件もあった。それに、会社の中には、婚約どころか、ふたりがつきあっている事実さえ未だに知らない人間もいるから、仮にも独身女性であるワタナベさんに伝言を頼むわけにはいかなかったのである。
「……じゃ、そろそろ会社に行ってくるから。何か欲しい物、ある?」
「…………」
ヤマダくんは無言で首を振った。声を出すのも億劫だったのだ。
「なるべく早く帰ってくるから。……無理しないでね」
手を振って、ワタナベさんがドアの向こうへ顔を引っ込める。バタン、とドアが閉められた。キッチンや洗面所、あるいは玄関の方から、シェアメイトたちが朝の支度を整え、三々五々出勤していく物音が伝わってきた。各自の出勤時間は人それぞれだが、『バーデン-H』では入居時の面接で基本的に昼勤者に限定している。生活時間のきょくたんに違う入居者がいると、共同生活の上で何かと不都合が生じるからだ。ベッドの中で耳にする出勤時間帯の喧騒は、何となく新鮮なものに感じられた。
ベッドサイドの時計に目をやると、7時40分――会社に電話するにはまだ早すぎる。
(……もうひと眠りするか)
そう考えて、ヤマダくんはふたたび瞼を閉じた。
……ふいに、鼻腔をくすぐる匂いを感じた。空っぽの胃袋を刺激する、食べ物の匂いだった。ヤマダくんがかすかに身じろぎすると、匂いのする方から声がかけられた。
「……あ。起こしちゃいましたぁ?」
甘ったるく語尾を伸ばす、独特のアニメ声だ。
「んー…………?」
半分寝ぼけたまま、ヤマダくんが音程だけで質問をぶつける。「どうした? 何故、この部屋にいるんだ?」というニュアンスの問いかけだった。
「えっと、お腹が空いてるんじゃないかと思ってぇ……」
当たり前のようにそう答えながら、声の主――202号室のマナセさんは手にしたお盆を見せた。お盆の上では、一人用の土鍋がぐつぐつと音を立てている。
「お粥ですぅ。冷めないうちにどうぞぉ……」
にっこりとお盆を差し出してみせるマナセさんに、ヤマダくんはベッドの中でいささか困惑していた。
もちろん、恋人でもない彼女にこんなことをしてもらう理由はない。だが、この場はひとまず受け取らないことにはどうにも収まらないような雰囲気だった。狙ってやっているなら大したタマだが、おそらくは天然なのだろう。
ヤマダくんは意を決して、ベッドに上体を起こすと、土鍋のお盆を受け取った。それから、マナセさんの目を正面から見て、ゆっくりと言い聞かせることにした。
――ありがとう。その気遣いはとてもうれしい。でも、こんなことをしてはいけない。もし、こういうことをする場合は、相手と特別な関係にあるか、一対一ではないときだけにしなさい……。
痛む咽喉で、発声に苦労しながら、ヤマダくんは諄々と説いた。
――キミは純粋な厚意でやってくれているんだろうけど、相手も誤解するし、周囲も誤解する。特に、こういう集団生活の場では、つまらん誤解で人間関係がギクシャクしてくるのがいちばん怖いんだ……。
しかし――。
「えー、でもぉ……」
マナセさんは唇を尖らせると、拗ねたようにこう言ってのけた。
「誤解とかぁ、そういうんじゃなくてぇ……」
「……」
「わたしはぁ……ヤマダさんのこと、好きですよ?」
「………?」
「ヤマダさんとぉ……特別な関係……に、なりたいと、思ってますよ?」
「……………ッ!?」
そのとき――。
遅まきながら、本当に遅まきながら――ヤマダくんはものすごく根本的なことに気づいたのである。
(この娘は……おれとワタナベさんのことを……気づいてなかったのか!?)
たしかに、ことさら改まってふたりの関係を説明したりはしなかったが――「それぐらい、見てりゃわかるだろう? いちいち言わせんな。察しろよ」というのがヤマダくんの本音であった。それがどうやら、マナセさんにはまったく伝わっていなかったらしいのだ。なんだかんだで、半年近くもひとつ屋根の下で暮らしているにもかかわらず……。
(やれやれ……これはいったい、どこから説明したものか……?)
ここまでくると「天然」だの「空気が読めない」だのというレベルではない。ヤマダくんも詳しくは知らないが、「アスペルガー症候群」とやらを疑ってみる必要もありそうだ。
ともあれ、問題点ははっきりした。ただし――ある意味、そのためにかえって厄介なことになったという気がしないでもない、ヤマダくんであった。
(つづく)
シェアハウス大家さん倶楽部について
新着コンテンツ
-
第144回 2026年とシェアハウス
2026-1-15 -
第143回 変化の時代とシェアハウス
2025-12-19 -
第142回 光明とシェアハウス
2025-11-17 -
第141回 抵抗感とシェアハウス
2025-10-16 -
第140回 未来予想図とシェアハウス
2025-9-16 -
第139回 不動産市況とシェアハウス2025夏
2025-8-16 -
第138回 公的支援とシェアハウス
2025-7-15 -
第137回 変わらぬ魅力とシェアハウス
2025-6-16 -
第136回 「不都合な真実」とシェアハウス
2025-5-16 -
第135回 時の流れとシェアハウス
2025-4-17
〜シェアハウス事業を企画から運営まで、トータルにサポート〜
運営会社:株式会社シェアスタイル | シェアハウス資産運用のご相談はこちら | シェアハウス管理物件のご紹介はこちら | 採用情報
Copyright © 2006-2015 ShareStyle Co.,Ltd. All Rights Reserved.