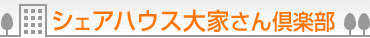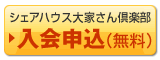第57話 ヤマダくん、たじろぐ!
「この間のことは、本当にごめんなさいね……」
テーブルに手を突いて深々と頭を下げてくる相手に、ヤマダくんは少々居心地悪そうに答える。
「いえ、まあ、済んだ話ですから……」
「そういうワケにもいかないわよ。一時はあたし、もう出て行かなきゃならないかと思ってたくらいだし」
そう言いながらも、相手はどこかサバサバした口調であった。本当にそうなっていたかもしれない――そう思うと、ヤマダくんとしても軽く流すこともできない。
何はともあれ、そうならずに済んでよかったと、ホッと胸を撫で下ろしているヤマダくんであった。
――K-駅前の喫茶店。
ヤマダくんはこの日、彼をオーナーとする2軒目のシェアハウス『バーデン-K』の元オーナーにして現シェアメイトリーダー、サクライさんと向かい合って座っていた。
テーブルに手を突いてしおらしく詫びる年長の女性の姿を見ながら、ヤマダくんは、1ヶ月半ほど前の彼女とのやりとりを思い出していた。
あのとき――。
「じゃあさ、あたしにどうしろって言いたいワケ?」
その日のサクライさんの機嫌はすこぶる悪かった。というより、理不尽さに怒っているように見えた。自分は何も間違ったことはしていない、なのに、どうして自分だけが責められなければいけないのか、と。
その気持ちは、ヤマダくんにも理解できた。理解できるだけに、何ともやりきれない思いを味わっていたのも事実だった。それでも、立場上言わなければならないことがある。ヤマダくんが絶対に正しいわけではない、サクライさんが絶対に間違っているわけでもない。ただ、この場合はヤマダくんの主張に分があることは確かなのだ。
『バーデン-K』のリビングで、掘りごたつをはさんで2人は対峙していた。ヤマダくんの傍らには、恋人でありハウスの共同経営者であるワタナベさんが、はらはらしながら2人を見つめている。そして、サクライさんの横には、オブザーバーとして管理会社のオオシマ女史が同席していた。
「我々としては、キムラさんのところの家庭の事情に口をはさむつもりはありませんし、サクライさんがアキヒロくんの面倒を見てくれるのはものすごくありがたいことだと思ってます。ただ……」
さすがに言いよどんだヤマダくんは、ちら、とオオシマ女史に視線を向けた。が、オオシマ女史が無言でうなずくのを見てとると、意を決したように先を続ける。
「あなた個人の考えはともかく――シェアハウス『バーデン-K』としては、アキヒロくんにももう少し、他の住人との距離をわきまえて行動してもらいたいと考えています」
「そんなの……3つやそこらの子どもに、そんなこと言っても無理よ!」
サクライさんがたまりかねたように叫んだ。
「それを決めるのはあなたではないはずですよ、サクライさん」
思わず興奮する女傑に、すかさず水をかけるように口をはさんだのはオオシマ女史であった。オブザーバーという立場にもかかわらず、敢えて横から口出ししてきたのは、ここで第三者が割って入らなければ余計事態がこじれる――という咄嗟の判断だったのだろう。
「そもそも、最初に幼い子連れのキムラさんをハウスに受け入れる、ということについて、他のシェアメイトの皆さんときちんと話し合われたのですか……?」
感情を入れず、淡々と指摘するオオシマ女史の言葉に、サクライさんは鼻白みつつも沈黙せざるを得なかった。
――そう。
今回の問題の根本には、サクライさんの独断専行があったのである。彼女が肝っ玉母さんよろしく「よしきた!」とばかりに受け入れを即断した――正確には、自ら買って出たのが、キムラさん母子をめぐる問題のそもそもの発端であった。サクライさんが以前のまま、シェアハウスのオーナーであったなら、それもまたやむなしであったかもしれない。どんな住人を受け入れようが、その結果ハウスにどんな問題が起ころうが、オーナーであればそれは自己責任の範疇である。「嫌なら出て行けばいい」と、極論すればそう言ってしまえるだけの根拠がそこにはあった。
だが、今のサクライさんは、要するに一介の賃借人に過ぎない。他のシェアメイトたちの世話役、シェアメイトリーダーとしてもろもろの雑務を引き受けてくれてはいるし、その点は配慮してある程度彼女の裁量に任せている部分もあるのだが――だからといって、何でもかんでも彼女のやりたいようにやっていいということではない。特に、他のシェアメイトに対して「これがこのハウスの方針だ。ここに住む限りは方針に従ってもらう」などという権限は、少なくとも現オーナーであるヤマダくんは与えた覚えはないのである。
けっきょくのところ、元オーナーであり、年長者であり、シェアハウスオーナーとしても先輩に当たるサクライさんに対して、ヤマダくんがついつい遠慮して、言いたいことも言えなくなっていたことが、ここまで事態をこじれさせてしまったともいえる。
「……たしかに」
先ほどまで激高寸前のテンションだったサクライさんは、急に憑き物が落ちたようにトーンダウンした。
「あたしは好きでアキくんの面倒見てるけど……他の子たちにも同じようにしろと言う権利は、あたしにはないんだわね……」
「サクライさん……」
何ごとか言いかけたヤマダくんを制して、そこまで黙って聞いていたワタナベさんが口を開いた。
「サクライさん。小さい子どもが騒いだりぐずったりするのは、それは仕方がないことですし、それを頭ごなしに否定したり、キムラさんたちに出て行けとかそういうことを言いたいわけではないんですよ。でも、いけないことをしたら叱るのも身近な大人の役目だと思いますし、せっかくひとつ屋根の下で暮らしているんですから、お互い、言いたいことは遠慮なく言える関係が望ましいと思うんです」
「……………?」
「だから、さっきオオシマさんがおっしゃった『話し合い』ですよ。『バーデン-K』の住人みんなで、納得のいくまで話し合えばいいんです」
ワタナベさんはこんこんと諭すように言った。
「もちろん、その話し合いの場には――」
そこで一瞬、ヤマダくんに目くばせしてみせる。
「私たちも出席します。だって、それもオーナーの仕事ですから」
――かくして、それから1週間後の週末に改めて時間を取り、『バーデン-K』の住人全員にプラス、ヤマダくんとワタナベさんが顔を揃えることになった。
言うまでもなく、キムラさんも膝にアキヒロくんを乗せて出席している。
開口一番、サクライさんは言った。
「――まず、皆さんにあたしからひと言、謝らせてください」
その言葉を聞いて、事情を知っているヤマダくんたちを除く住人一同がざわつく。サクライさんは構わず、言葉を続けた。
「キムラさん、アキヒロくんに対するあたしの考え方が間違っていたとは思いません。……でも、それを一方的に皆さんに押しつけるのは、どう考えても間違っていたとわかりました」
ごめんなさい、と頭を下げるサクライさんに続いて、ヤマダくんがその日の集まりの主旨を告げる。
「私たちとしても、皆さんにはご理解とご協力をお願いしたいと思っています。ただし、できる範囲で。無理なことは無理、イヤならイヤだと遠慮なくはっきり言ってください。今この場で言いづらければ、後で個人的に申し出ていただいても構いませんが……できれば、全員が顔を揃えたこの機会に、お互いに言いたいことは全部言ってスッキリしたいと思いませんか……?」
言い終えてから一同を見回すと、3号室のササキさんはうんうんと小さく頷いており、4号室のミゾグチさんあたりも明らかな反応があった。やがて――誰かが口火を切ったのをきっかけに、それぞれが明確に自分の意見を口にし始めたのである。
話し合いは、アキヒロくんという小さな男の子の住人が『バーデン-K』で共同生活を送る上で、注意するべきこと、お互いに守るべきルール、ルールを破った際のペナルティまで含めて、全員が納得するまでとことん続けられた。
何しろ女性専用ハウスのことなので、かなり赤裸々な話題も飛び出し、ヤマダくんとしてはいささか落ち着かない気分にさせられる場面もあったが――途中、退屈のあまり舟をこぎ出したアキヒロくんをキムラさんが自室で寝かしつける中断をはさみつつ、夜の更けるまで話し合いは続いた。
そして、最終的には、住人の誰も納得して受け入れられるだけの形で決着したのであった。
「今さらだけどさ、やっぱり子どものいる生活っていろいろ大変なんだな……」
その夜遅く――くたくたになりながらタクシーを拾って『バーデン-H』へ帰宅したヤマダくんは、同じく疲れ切った顔のワタナベさんに言った。
と――ぼやき半分の月並みな感想のつもりだったのに、意外な反応が返ってくる。
「子ども……欲しくないの?」
「……え?」
思わずたじろいだヤマダくんに向けて、
「――わたしは、欲しいと思ってるんだけど……?」
恋人の口から、不意打ちの爆弾発言が飛び出した。
(つづく)
テーブルに手を突いて深々と頭を下げてくる相手に、ヤマダくんは少々居心地悪そうに答える。
「いえ、まあ、済んだ話ですから……」
「そういうワケにもいかないわよ。一時はあたし、もう出て行かなきゃならないかと思ってたくらいだし」
そう言いながらも、相手はどこかサバサバした口調であった。本当にそうなっていたかもしれない――そう思うと、ヤマダくんとしても軽く流すこともできない。
何はともあれ、そうならずに済んでよかったと、ホッと胸を撫で下ろしているヤマダくんであった。
――K-駅前の喫茶店。
ヤマダくんはこの日、彼をオーナーとする2軒目のシェアハウス『バーデン-K』の元オーナーにして現シェアメイトリーダー、サクライさんと向かい合って座っていた。
テーブルに手を突いてしおらしく詫びる年長の女性の姿を見ながら、ヤマダくんは、1ヶ月半ほど前の彼女とのやりとりを思い出していた。
あのとき――。
「じゃあさ、あたしにどうしろって言いたいワケ?」
その日のサクライさんの機嫌はすこぶる悪かった。というより、理不尽さに怒っているように見えた。自分は何も間違ったことはしていない、なのに、どうして自分だけが責められなければいけないのか、と。
その気持ちは、ヤマダくんにも理解できた。理解できるだけに、何ともやりきれない思いを味わっていたのも事実だった。それでも、立場上言わなければならないことがある。ヤマダくんが絶対に正しいわけではない、サクライさんが絶対に間違っているわけでもない。ただ、この場合はヤマダくんの主張に分があることは確かなのだ。
『バーデン-K』のリビングで、掘りごたつをはさんで2人は対峙していた。ヤマダくんの傍らには、恋人でありハウスの共同経営者であるワタナベさんが、はらはらしながら2人を見つめている。そして、サクライさんの横には、オブザーバーとして管理会社のオオシマ女史が同席していた。
「我々としては、キムラさんのところの家庭の事情に口をはさむつもりはありませんし、サクライさんがアキヒロくんの面倒を見てくれるのはものすごくありがたいことだと思ってます。ただ……」
さすがに言いよどんだヤマダくんは、ちら、とオオシマ女史に視線を向けた。が、オオシマ女史が無言でうなずくのを見てとると、意を決したように先を続ける。
「あなた個人の考えはともかく――シェアハウス『バーデン-K』としては、アキヒロくんにももう少し、他の住人との距離をわきまえて行動してもらいたいと考えています」
「そんなの……3つやそこらの子どもに、そんなこと言っても無理よ!」
サクライさんがたまりかねたように叫んだ。
「それを決めるのはあなたではないはずですよ、サクライさん」
思わず興奮する女傑に、すかさず水をかけるように口をはさんだのはオオシマ女史であった。オブザーバーという立場にもかかわらず、敢えて横から口出ししてきたのは、ここで第三者が割って入らなければ余計事態がこじれる――という咄嗟の判断だったのだろう。
「そもそも、最初に幼い子連れのキムラさんをハウスに受け入れる、ということについて、他のシェアメイトの皆さんときちんと話し合われたのですか……?」
感情を入れず、淡々と指摘するオオシマ女史の言葉に、サクライさんは鼻白みつつも沈黙せざるを得なかった。
――そう。
今回の問題の根本には、サクライさんの独断専行があったのである。彼女が肝っ玉母さんよろしく「よしきた!」とばかりに受け入れを即断した――正確には、自ら買って出たのが、キムラさん母子をめぐる問題のそもそもの発端であった。サクライさんが以前のまま、シェアハウスのオーナーであったなら、それもまたやむなしであったかもしれない。どんな住人を受け入れようが、その結果ハウスにどんな問題が起ころうが、オーナーであればそれは自己責任の範疇である。「嫌なら出て行けばいい」と、極論すればそう言ってしまえるだけの根拠がそこにはあった。
だが、今のサクライさんは、要するに一介の賃借人に過ぎない。他のシェアメイトたちの世話役、シェアメイトリーダーとしてもろもろの雑務を引き受けてくれてはいるし、その点は配慮してある程度彼女の裁量に任せている部分もあるのだが――だからといって、何でもかんでも彼女のやりたいようにやっていいということではない。特に、他のシェアメイトに対して「これがこのハウスの方針だ。ここに住む限りは方針に従ってもらう」などという権限は、少なくとも現オーナーであるヤマダくんは与えた覚えはないのである。
けっきょくのところ、元オーナーであり、年長者であり、シェアハウスオーナーとしても先輩に当たるサクライさんに対して、ヤマダくんがついつい遠慮して、言いたいことも言えなくなっていたことが、ここまで事態をこじれさせてしまったともいえる。
「……たしかに」
先ほどまで激高寸前のテンションだったサクライさんは、急に憑き物が落ちたようにトーンダウンした。
「あたしは好きでアキくんの面倒見てるけど……他の子たちにも同じようにしろと言う権利は、あたしにはないんだわね……」
「サクライさん……」
何ごとか言いかけたヤマダくんを制して、そこまで黙って聞いていたワタナベさんが口を開いた。
「サクライさん。小さい子どもが騒いだりぐずったりするのは、それは仕方がないことですし、それを頭ごなしに否定したり、キムラさんたちに出て行けとかそういうことを言いたいわけではないんですよ。でも、いけないことをしたら叱るのも身近な大人の役目だと思いますし、せっかくひとつ屋根の下で暮らしているんですから、お互い、言いたいことは遠慮なく言える関係が望ましいと思うんです」
「……………?」
「だから、さっきオオシマさんがおっしゃった『話し合い』ですよ。『バーデン-K』の住人みんなで、納得のいくまで話し合えばいいんです」
ワタナベさんはこんこんと諭すように言った。
「もちろん、その話し合いの場には――」
そこで一瞬、ヤマダくんに目くばせしてみせる。
「私たちも出席します。だって、それもオーナーの仕事ですから」
――かくして、それから1週間後の週末に改めて時間を取り、『バーデン-K』の住人全員にプラス、ヤマダくんとワタナベさんが顔を揃えることになった。
言うまでもなく、キムラさんも膝にアキヒロくんを乗せて出席している。
開口一番、サクライさんは言った。
「――まず、皆さんにあたしからひと言、謝らせてください」
その言葉を聞いて、事情を知っているヤマダくんたちを除く住人一同がざわつく。サクライさんは構わず、言葉を続けた。
「キムラさん、アキヒロくんに対するあたしの考え方が間違っていたとは思いません。……でも、それを一方的に皆さんに押しつけるのは、どう考えても間違っていたとわかりました」
ごめんなさい、と頭を下げるサクライさんに続いて、ヤマダくんがその日の集まりの主旨を告げる。
「私たちとしても、皆さんにはご理解とご協力をお願いしたいと思っています。ただし、できる範囲で。無理なことは無理、イヤならイヤだと遠慮なくはっきり言ってください。今この場で言いづらければ、後で個人的に申し出ていただいても構いませんが……できれば、全員が顔を揃えたこの機会に、お互いに言いたいことは全部言ってスッキリしたいと思いませんか……?」
言い終えてから一同を見回すと、3号室のササキさんはうんうんと小さく頷いており、4号室のミゾグチさんあたりも明らかな反応があった。やがて――誰かが口火を切ったのをきっかけに、それぞれが明確に自分の意見を口にし始めたのである。
話し合いは、アキヒロくんという小さな男の子の住人が『バーデン-K』で共同生活を送る上で、注意するべきこと、お互いに守るべきルール、ルールを破った際のペナルティまで含めて、全員が納得するまでとことん続けられた。
何しろ女性専用ハウスのことなので、かなり赤裸々な話題も飛び出し、ヤマダくんとしてはいささか落ち着かない気分にさせられる場面もあったが――途中、退屈のあまり舟をこぎ出したアキヒロくんをキムラさんが自室で寝かしつける中断をはさみつつ、夜の更けるまで話し合いは続いた。
そして、最終的には、住人の誰も納得して受け入れられるだけの形で決着したのであった。
「今さらだけどさ、やっぱり子どものいる生活っていろいろ大変なんだな……」
その夜遅く――くたくたになりながらタクシーを拾って『バーデン-H』へ帰宅したヤマダくんは、同じく疲れ切った顔のワタナベさんに言った。
と――ぼやき半分の月並みな感想のつもりだったのに、意外な反応が返ってくる。
「子ども……欲しくないの?」
「……え?」
思わずたじろいだヤマダくんに向けて、
「――わたしは、欲しいと思ってるんだけど……?」
恋人の口から、不意打ちの爆弾発言が飛び出した。
(つづく)
シェアハウス大家さん倶楽部について
新着コンテンツ
-
第123回 ライフステージとシェアハウス
2024-4-16 -
第122回 景気回復とシェアハウス2024
2024-3-15 -
第121回 生活困窮者とシェアハウス
2024-2-15 -
第120回 震災とシェアハウス2024
2024-1-15 -
第119回 プレスリリースとシェアハウスその2
2023-12-15 -
第118回 住宅難とシェアハウス
2023-11-30 -
第117回 プレスリリースとシェアハウス
2023-10-15 -
第116回 アンケート調査とシェアハウス
2023-9-15 -
第115回 防災とシェアハウス
2023-8-15 -
第114回 猛暑とシェアハウス
2023-7-15
〜シェアハウス事業を企画から運営まで、トータルにサポート〜
運営会社:株式会社シェアスタイル | シェアハウス資産運用のご相談はこちら | シェアハウス管理物件のご紹介はこちら | 採用情報
Copyright © 2006-2015 ShareStyle Co.,Ltd. All Rights Reserved.