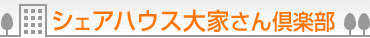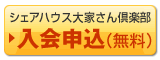第76話 ヤマダくん、引き取る?
「――つまりは、そういうことなんですが……」
つい先日とは、まるっきり立場も口調も変えて、ヤマダくんは言った。
「どうかひとつ、皆さんの忌憚のないご意見という奴を……」
大仰な物言いと揉み手をせんばかりのへりくだりようは、もちろん、ジョークに紛らわせようという意図的な態度だったが、そればかりではない。じつは案外、これが重要な件だということを相手に悟らせないためのテクニックでもあった。
とはいえ、そんなヤマダくんの腹の内など、この場に集まった連中にとってはとっくにお見通しだったのだが……。
「つまり、あなたはこう言いたいわけね――?」
冷静、というよりは、いっそ冷ややかといっていい口調で、ヤマダくんの新妻が一同を代表して口を開いた。
「“この子”を、『バーデン-S』の新しい家族に加えたい、と……」
その場にいる一同の視線が、彼女の指し示す“この子”に集中する。と、その視線の圧におびえるように、“この子”――全身を淡い茶褐色の長毛に覆われた、ゴールデン・レトリバー種の大型犬がぶるる……っと身震いする。
「うわッ……!」
反射的に声を上げたヤマダくんだったが――幸い、手入れが行き届いているとみえて、抜け毛や埃が飛び散るようなこともなかった。そのことを確認すると、ヤマダくんは気を取り直して、おそるおそる妻の質問に答える。
「うん……まあ…………」
その、いかにも気まずそうなニュアンスの回答に合わせて。
「クゥ〜〜ン」
甘えるようにゴールデン・レトリバーが鼻を鳴らした。
7月上旬――ヤマダくんが抜き打ちで『バーデン-H』のようすを見に行き、そこでシェアメイトリーダーのイトウくんがこっそり犬を飼っているのを発見した、翌日のことである。
その前日、ヤマダくんはイトウくんを厳しく問い詰め、前後の事情を残らず聴きだした。
イトウくんの元カノだった女性が、飼えもしないのに、当時彼女が住んでいたペット禁止のワンルームマンションでこっそり仔犬を飼いだしてしまったこと。
しかも、ものの2〜3ヶ月で世話に飽きてしまい、管理人にバレたのをきっかけに、彼氏だったイトウくんに犬を丸投げしたこと。
イトウくんがそのとき引き受けていなければ、今頃は保健所行きになっていたこと。
オーナーであるヤマダくんがはっきり「ダメだ」と言ったにもかかわらず、それに逆らってまで犬を室内で飼っていたことは、たしかに問題だ。しかし、事情を聞けば情状酌量の余地はありそうだし、何より、『バーデン-H』の他の入居者たちが、誰もこの件についてオーナーであるヤマダくんたちに連絡してこなかった、というのは大きい。犬を飼うことについて、イトウくんがたとえば「ヤマダさんの許可はもらってるから……」というふうにゴマ化していたのだとしても、不満があればきっと報告してくるはずだ。特に2階の女性陣は、ヤマダくんに直接は言いにくくても、先日まで女性入居者を代表する立場だったヤマダ夫人にならいくらでも言いたいことが言えるはずだった。
逆に言えば――彼ら彼女らが何も言ってこなかったのは、日常生活において特に大きな問題はなかった、ということなのではないだろうか……?
そこまで考えた上で、ふと一計を案じたヤマダくんは、イトウくんに彼の覚悟のほどを訊ねてみることにした。
「何度も言うように、この『バーデン-H』はペット禁止。このルールに変更はない。したがって……イトウくんが選ぶべき道は2つに1つだ。犬を飼うか、ここから出ていくか――?」
「…………」
「もちろん、君に『出ていけ』と一方的に言うつもりはないよ。それに、『犬を保健所に連れていけ』とも言わない。ただ、犬を飼い続けたいならここに住んだままだと困るし、ここに住み続けたいなら犬を飼ったままだと困る――」
「…………………はい」
イトウくんは、咽喉の奥からかろうじて絞りだしたような声を発した。よほど苦渋の判断なのだろう、何度も何度もためらいながら、いずれかの返事を口に出そうとする。が、そこにヤマダくんがすかさず割って入った。
「ただし――もし君が出ていくほうを選んだ場合、『バーデン-H』の運営にいくつかの不都合が生じることになる。それはこちらにとっても、他の入居者にとっても望ましくない」
「じゃ……どうしろと………?」
ヤマダくんの真意をつかみかねて、イトウくんが問う。ヤマダくんは即答した。
「イトウくんにはこのまま残ってもらい、『バーデン-H』の運営に協力してもらう。それと、ルール違反のペナルティとして、共有スペースの原状回復を自腹で行ってもらいます」
「? それはかまいませんが……?」
「で、この犬の引き取り手についてなんだけど……」
「…………」
イトウくんの顔に緊張が走る。こっそり部屋で飼い始めてから1ヶ月余り――もはや、完全に情が移ってしまっているらしい。
「その前にひとつ訊いておきたい。――イトウくんは、この犬に名前を付けたの?」
「………いいえ」
イトウくんの返事に、ヤマダくんは満足げに頷いた。もし自分で飼い続けるつもりなら名前を付けたであろうから、少なくとも「引き取り手を探しているが、なかなか見つからない」というイトウくんの言葉はウソではないということだ。
「……正直、この場で安請け合いすることはできないんだけど――犬の引き取り手については、おれのほうにアテがないこともないんだ」
「え……?」
ヤマダくんのその言葉に、イトウくんの顔がパッと明るくなった。それから一拍置いて、ちょっとさみしげな翳がさす。どうやら保健所行きは免れそうだが、犬の引き取り手が決まったら、イトウくんにとっては犬との永遠のお別れということになるからだろう。
「……で、だ。これはイトウくんにとっても、決して悪い話じゃないと思うんだけど――」
ヤマダくんがふいに、声をひそめて何ごとかささやく。その言葉を聞くうちに、イトウくんの表情がみるみる輝きはじめるのだった。
――そして、その翌朝。
前夜はS市内のペットホテルに犬を預け、何ごともなかったように帰宅したヤマダくんは、『バーデン-S』のすべての住人をリビングに集めて言った。全員に関わる問題なので、きちんと話し合って決めたい。急な話で申し訳ないが、ぜひ時間を空けてほしい――と。
そして、全員の都合のつく時間帯をセッティングした上で、預けておいたペットホテルから犬を連れてきて、会議の場で全住人と引き合わせることにしたのである。
ちなみに、犬をホテルから連れてくる役目は、イトウくんに協力してもらった。さらに、この犬の素性、ここに至るまでの経緯については、イトウくんの口から正直に包み隠さず話してもらう。そうして事情を知ってもらった上で、「こいつを『バーデン-S』で飼ってやりたいんだが、みんなは賛成してくれるかな?」と訊いてみるつもりだった。
この『バーデン-S』には、それなりの広さの庭もある。庭はブロック塀で囲われ、近隣の家々ともある程度離れている。『バーデン-H』のような都心部と違い、土も緑も身近にある。つまり、犬を庭で飼うことは十分できる。
だが――たとえ、この家のオーナーがヤマダくん夫妻であるにしても、住んでいるのは三世帯計8人の家族であり、彼らの意向を無視して勝手に犬を飼うことはできない。たとえば――今まで特に聞いたことはないから、たぶん大丈夫だろうが――子どもが犬猫の体毛アレルギーだという可能性だってゼロではない。奥さん方はもちろん、旦那連中にしても、何かの幼児体験により大人になっても犬が怖いという人はけっこういる。ヤマダくん自身を除いた7人の住人のうち、ひとりでも反対する人がいたら、『バーデン-S』で犬を飼うのはあきらめるしかない……。
とはいえ――けっきょくのところ、それは杞憂でしかなかった。
「……いいんじゃないの?」
アオノさんがあっさりといい、興味津々で犬に近づこうとするノゾミちゃんをあわてて抱き寄せながら、アオノ夫人も満面の笑みで頷いてみせる。イシザキくんなぞ、逆に「何の問題があるの?」と言わんばかりの表情だったし、無邪気にキャッキャと喜んでいるソウタくんを抱いたイシザキ夫人もにこにこと嬉しそうだ。そしてもちろん、ヤマダくんの新妻はさっそく犬に近づいて、お腹のあたりの柔らかい毛並みを撫でている。
「――じゃあ、満場一致、ということで。今日からこいつは、『バーデン-S』の新しい家族の一員になりました」
ヤマダくんがそう宣言し、一同が拍手する。
「ねえ、“こいつ”っていうけど、名前はないの?」
ヤマダ夫人の問題提起に、すかさず他の家族も反応する。
「そうだ。まずは名前を付けてやらないと――」
「男の子? 女の子?」
「ごはんとか、お散歩とか、後でローテーション決めとかないと……」
――あっさりと家族の一員として受け入れられている犬の姿を見ているイトウくんの背中は、さすがにちょっと寂しそうに見えた。そんなイトウくんに、ヤマダくんは慰めるように言った。
「――まあ、ここに来ればいつでも会えるからさ。来る前に連絡してくれれば、いつでも歓迎するよ」
「え、ホントですか……?」
「あ、そうだ。何なら、『バーデン-H』の報告を兼ねて、月イチくらいでこっちに来る?」
まるで名案を思いついたような口調で、真顔でそんなことを言うヤマダくんだった。
(つづく)
つい先日とは、まるっきり立場も口調も変えて、ヤマダくんは言った。
「どうかひとつ、皆さんの忌憚のないご意見という奴を……」
大仰な物言いと揉み手をせんばかりのへりくだりようは、もちろん、ジョークに紛らわせようという意図的な態度だったが、そればかりではない。じつは案外、これが重要な件だということを相手に悟らせないためのテクニックでもあった。
とはいえ、そんなヤマダくんの腹の内など、この場に集まった連中にとってはとっくにお見通しだったのだが……。
「つまり、あなたはこう言いたいわけね――?」
冷静、というよりは、いっそ冷ややかといっていい口調で、ヤマダくんの新妻が一同を代表して口を開いた。
「“この子”を、『バーデン-S』の新しい家族に加えたい、と……」
その場にいる一同の視線が、彼女の指し示す“この子”に集中する。と、その視線の圧におびえるように、“この子”――全身を淡い茶褐色の長毛に覆われた、ゴールデン・レトリバー種の大型犬がぶるる……っと身震いする。
「うわッ……!」
反射的に声を上げたヤマダくんだったが――幸い、手入れが行き届いているとみえて、抜け毛や埃が飛び散るようなこともなかった。そのことを確認すると、ヤマダくんは気を取り直して、おそるおそる妻の質問に答える。
「うん……まあ…………」
その、いかにも気まずそうなニュアンスの回答に合わせて。
「クゥ〜〜ン」
甘えるようにゴールデン・レトリバーが鼻を鳴らした。
7月上旬――ヤマダくんが抜き打ちで『バーデン-H』のようすを見に行き、そこでシェアメイトリーダーのイトウくんがこっそり犬を飼っているのを発見した、翌日のことである。
その前日、ヤマダくんはイトウくんを厳しく問い詰め、前後の事情を残らず聴きだした。
イトウくんの元カノだった女性が、飼えもしないのに、当時彼女が住んでいたペット禁止のワンルームマンションでこっそり仔犬を飼いだしてしまったこと。
しかも、ものの2〜3ヶ月で世話に飽きてしまい、管理人にバレたのをきっかけに、彼氏だったイトウくんに犬を丸投げしたこと。
イトウくんがそのとき引き受けていなければ、今頃は保健所行きになっていたこと。
オーナーであるヤマダくんがはっきり「ダメだ」と言ったにもかかわらず、それに逆らってまで犬を室内で飼っていたことは、たしかに問題だ。しかし、事情を聞けば情状酌量の余地はありそうだし、何より、『バーデン-H』の他の入居者たちが、誰もこの件についてオーナーであるヤマダくんたちに連絡してこなかった、というのは大きい。犬を飼うことについて、イトウくんがたとえば「ヤマダさんの許可はもらってるから……」というふうにゴマ化していたのだとしても、不満があればきっと報告してくるはずだ。特に2階の女性陣は、ヤマダくんに直接は言いにくくても、先日まで女性入居者を代表する立場だったヤマダ夫人にならいくらでも言いたいことが言えるはずだった。
逆に言えば――彼ら彼女らが何も言ってこなかったのは、日常生活において特に大きな問題はなかった、ということなのではないだろうか……?
そこまで考えた上で、ふと一計を案じたヤマダくんは、イトウくんに彼の覚悟のほどを訊ねてみることにした。
「何度も言うように、この『バーデン-H』はペット禁止。このルールに変更はない。したがって……イトウくんが選ぶべき道は2つに1つだ。犬を飼うか、ここから出ていくか――?」
「…………」
「もちろん、君に『出ていけ』と一方的に言うつもりはないよ。それに、『犬を保健所に連れていけ』とも言わない。ただ、犬を飼い続けたいならここに住んだままだと困るし、ここに住み続けたいなら犬を飼ったままだと困る――」
「…………………はい」
イトウくんは、咽喉の奥からかろうじて絞りだしたような声を発した。よほど苦渋の判断なのだろう、何度も何度もためらいながら、いずれかの返事を口に出そうとする。が、そこにヤマダくんがすかさず割って入った。
「ただし――もし君が出ていくほうを選んだ場合、『バーデン-H』の運営にいくつかの不都合が生じることになる。それはこちらにとっても、他の入居者にとっても望ましくない」
「じゃ……どうしろと………?」
ヤマダくんの真意をつかみかねて、イトウくんが問う。ヤマダくんは即答した。
「イトウくんにはこのまま残ってもらい、『バーデン-H』の運営に協力してもらう。それと、ルール違反のペナルティとして、共有スペースの原状回復を自腹で行ってもらいます」
「? それはかまいませんが……?」
「で、この犬の引き取り手についてなんだけど……」
「…………」
イトウくんの顔に緊張が走る。こっそり部屋で飼い始めてから1ヶ月余り――もはや、完全に情が移ってしまっているらしい。
「その前にひとつ訊いておきたい。――イトウくんは、この犬に名前を付けたの?」
「………いいえ」
イトウくんの返事に、ヤマダくんは満足げに頷いた。もし自分で飼い続けるつもりなら名前を付けたであろうから、少なくとも「引き取り手を探しているが、なかなか見つからない」というイトウくんの言葉はウソではないということだ。
「……正直、この場で安請け合いすることはできないんだけど――犬の引き取り手については、おれのほうにアテがないこともないんだ」
「え……?」
ヤマダくんのその言葉に、イトウくんの顔がパッと明るくなった。それから一拍置いて、ちょっとさみしげな翳がさす。どうやら保健所行きは免れそうだが、犬の引き取り手が決まったら、イトウくんにとっては犬との永遠のお別れということになるからだろう。
「……で、だ。これはイトウくんにとっても、決して悪い話じゃないと思うんだけど――」
ヤマダくんがふいに、声をひそめて何ごとかささやく。その言葉を聞くうちに、イトウくんの表情がみるみる輝きはじめるのだった。
――そして、その翌朝。
前夜はS市内のペットホテルに犬を預け、何ごともなかったように帰宅したヤマダくんは、『バーデン-S』のすべての住人をリビングに集めて言った。全員に関わる問題なので、きちんと話し合って決めたい。急な話で申し訳ないが、ぜひ時間を空けてほしい――と。
そして、全員の都合のつく時間帯をセッティングした上で、預けておいたペットホテルから犬を連れてきて、会議の場で全住人と引き合わせることにしたのである。
ちなみに、犬をホテルから連れてくる役目は、イトウくんに協力してもらった。さらに、この犬の素性、ここに至るまでの経緯については、イトウくんの口から正直に包み隠さず話してもらう。そうして事情を知ってもらった上で、「こいつを『バーデン-S』で飼ってやりたいんだが、みんなは賛成してくれるかな?」と訊いてみるつもりだった。
この『バーデン-S』には、それなりの広さの庭もある。庭はブロック塀で囲われ、近隣の家々ともある程度離れている。『バーデン-H』のような都心部と違い、土も緑も身近にある。つまり、犬を庭で飼うことは十分できる。
だが――たとえ、この家のオーナーがヤマダくん夫妻であるにしても、住んでいるのは三世帯計8人の家族であり、彼らの意向を無視して勝手に犬を飼うことはできない。たとえば――今まで特に聞いたことはないから、たぶん大丈夫だろうが――子どもが犬猫の体毛アレルギーだという可能性だってゼロではない。奥さん方はもちろん、旦那連中にしても、何かの幼児体験により大人になっても犬が怖いという人はけっこういる。ヤマダくん自身を除いた7人の住人のうち、ひとりでも反対する人がいたら、『バーデン-S』で犬を飼うのはあきらめるしかない……。
とはいえ――けっきょくのところ、それは杞憂でしかなかった。
「……いいんじゃないの?」
アオノさんがあっさりといい、興味津々で犬に近づこうとするノゾミちゃんをあわてて抱き寄せながら、アオノ夫人も満面の笑みで頷いてみせる。イシザキくんなぞ、逆に「何の問題があるの?」と言わんばかりの表情だったし、無邪気にキャッキャと喜んでいるソウタくんを抱いたイシザキ夫人もにこにこと嬉しそうだ。そしてもちろん、ヤマダくんの新妻はさっそく犬に近づいて、お腹のあたりの柔らかい毛並みを撫でている。
「――じゃあ、満場一致、ということで。今日からこいつは、『バーデン-S』の新しい家族の一員になりました」
ヤマダくんがそう宣言し、一同が拍手する。
「ねえ、“こいつ”っていうけど、名前はないの?」
ヤマダ夫人の問題提起に、すかさず他の家族も反応する。
「そうだ。まずは名前を付けてやらないと――」
「男の子? 女の子?」
「ごはんとか、お散歩とか、後でローテーション決めとかないと……」
――あっさりと家族の一員として受け入れられている犬の姿を見ているイトウくんの背中は、さすがにちょっと寂しそうに見えた。そんなイトウくんに、ヤマダくんは慰めるように言った。
「――まあ、ここに来ればいつでも会えるからさ。来る前に連絡してくれれば、いつでも歓迎するよ」
「え、ホントですか……?」
「あ、そうだ。何なら、『バーデン-H』の報告を兼ねて、月イチくらいでこっちに来る?」
まるで名案を思いついたような口調で、真顔でそんなことを言うヤマダくんだった。
(つづく)
シェアハウス大家さん倶楽部について
新着コンテンツ
-
第144回 2026年とシェアハウス
2026-1-15 -
第143回 変化の時代とシェアハウス
2025-12-19 -
第142回 光明とシェアハウス
2025-11-17 -
第141回 抵抗感とシェアハウス
2025-10-16 -
第140回 未来予想図とシェアハウス
2025-9-16 -
第139回 不動産市況とシェアハウス2025夏
2025-8-16 -
第138回 公的支援とシェアハウス
2025-7-15 -
第137回 変わらぬ魅力とシェアハウス
2025-6-16 -
第136回 「不都合な真実」とシェアハウス
2025-5-16 -
第135回 時の流れとシェアハウス
2025-4-17
〜シェアハウス事業を企画から運営まで、トータルにサポート〜
運営会社:株式会社シェアスタイル | シェアハウス資産運用のご相談はこちら | シェアハウス管理物件のご紹介はこちら | 採用情報
Copyright © 2006-2015 ShareStyle Co.,Ltd. All Rights Reserved.