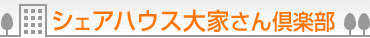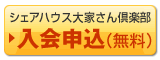第79話 ヤマダくん、ハシゴする!
「は〜い、それじゃみんな、準備はいいかな? ………メリークリスマス!」
「メリークリスマ〜ス!!」
司会者の音頭に合わせて、テーブルを囲んで居並ぶ10人ほどのメンバーがいっせいに唱和する。めいめいが好みの飲み物を満たしたグラスを掲げ、周りの者たちのグラスに次々に合わせる。カチン、チン、チン……と澄んだ音がそこかしこで響いた。
そのようすを見渡しながら、ヤマダくんは心の中でかすかな寂しさを感じていた。
(――やっぱり、去年までと比べると今年はちょっと、な……)
1年前のクリスマスパーティは、じつに華やかに盛り上がった。2年前はごく普通のパーティだったが、3年前には人数が今の倍近くいて、リビングに収まり切れないほどだった。それらに比べてしまうと、参加人数からしても、今年はややこぢんまりとした感が強い。
(…………まあ、それもしょうがないか)
1年前のクリスマスは、ちょうど、その直前に急遽決まったヤマダくんと、当時は婚約者であったワタナベさんとの挙式の前祝い、という意味合いもあって、頭数は同じくらいでも、個々のメンバーのテンションが異常なくらい高かった。また、3年前には、当時ヤマダくんが所有していた2軒目のシェアハウス『バーデン-K』との合同パーティという形にしたため、この『バーデン-H』の入居者以外のゲスト参加が多かった。
それに対して、今年は基本的に入居者のみの参加であり、むしろ、オーナーとして参加したヤマダくん自身が唯一のゲスト枠である。去年のパーティではヤマダくんの隣にいた妻は、今ごろ、ここから電車で7駅ほど離れた『バーデン-S』で、シェアメイトたちと一緒に夫の帰りを待っていることだろう。
(――やっぱり、今年も合同パーティにしちゃえばよかったかな?)
正直、そう思わないでもなかったが――どちらを会場にするにしても、ドアツードアで片道45分以上の距離の移動は、お互い負担が大きい。かといって、双方の中間くらいの地点にパーティ会場を借りる、というのも、それはそれで趣旨が違うような気がする。なんだかんだ言っても、年に一度のクリスマスパーティなのだから、気の置けない者同士が、“我が家”で騒ぐのが一番だろう。
テーブルの上には、チキンやフライドポテト、キッシュやチーズの盛り合わせなどの皿が所狭しと並んでいる。今年はシャンパンの用意はなかったが、ワインクーラーにはよく冷えた白ワインが3本。キッチンの冷蔵庫には缶ビールや日本酒も控えている。クリスマスらしい飾りつけとしては、玄関とリビングの壁にクリスマスモールが架けられていた。
「――ヤマダさ〜ん、飲んでますか〜?」
そう言いながらワインのボトルを構える101号室のイトウくん――現・シェアメイトリーダーであり、今年のパーティの主催者――に、まだ半分ほど残っている自分のグラスを突き出しながら、ヤマダくんは、何となくアウェー感を覚えずにはいられなかった。
――話は2週間ほど前にさかのぼる。
その日、ヤマダくんは、イトウくんからの“定例報告”の電話を受けていた。
『バーデン-H』のシェアメイトリーダーであるイトウくんは、ハウスや住人たちのようすについて、毎月第1土曜日と第3土曜日の夜に電話で報告してくることになっていた。もともとは、月1回ペースでヤマダくんが『バーデン-H』まで顔を出すことにしていたのだが、いつの間にやら月2回の電話報告で済ませるようになったのである。ヤマダくんとしては、そろそろ電話も月1回でいいか、と考え始めていた。
「――そういえば、今年のクリスマスはどうします?」
そのイトウくんの言葉で、ヤマダくんはようやく、今年ももうそんな時期かと思い至った。
「どうするって……?」
怪訝そうに訊き返すヤマダくんに、
「ヤマダさんたちも参加されますよね?」
さも当たり前のことのようにイトウくんは言う。実際、彼にとっては当たり前なのだろう。ヤマダくんたちが『バーデン-S』へ引っ越してから、まだ1年とは経っていない。もともとオーナーなのだし、引っ越したといっても参加資格は十分にある。というより、ここ数ヶ月、こちらへ顔を出していないのだから、クリスマスくらいは顔を見せるべきだろう、と考えているようだった。
少し考えてから、ヤマダくんは答えた。
「――とりあえず、俺は参加させてもらうよ。他の者は、こちらで話し合ってから返事をする。ほら、まだ小さい子もいるし……」
「わかりました、お返事待ってます。ワタナ……いえ、奥さんも、来られるようでしたら、ぜひご一緒に」
うっかり旧姓で呼びそうになったのをあわてて訂正しつつ、イトウくんはそう言って電話を切った。
「……あ、」
通話の切れたスマホを見つめていたヤマダくんが、ふと、何かに気づいたように声を漏らした。
(パーティの日程、聞くの忘れてた…………ま、いっか)
「ん。わたしは遠慮しとく」
即答だった。
「あなただけ、行ってらっしゃいよ。みんなにもよろしく」
妻の返事はある意味、ヤマダくんの予想通りだった。彼女の意識としては、もう『バーデン-H』は“よそさまの家”なのだろう。この『バーデン-S』こそが我が家であり、よその家のクリスマスパーティに顔を出すのは気が進まないということのようだった。
「いや、でも、タバタさんとかもいるわけだし……」
ヤマダくんは、念の為、というつもりで妻の旧友の名前を挙げた。203号室のタバタさんは妻の学生時代からの親友であり、もとはと言えば妻の誘いで『バーデン-H』に入居した、という経緯がある。
「うーん……何て言うかな? オンナはいろいろと面倒くさいのよ」
口頭ではあったが、「オンナ」とカタカナで発音したニュアンスが伝わってくる。いつにない妻の生々しい声音に、ヤマダくんはちょっとドギマギする。
「わたしが結婚しちゃったから、ちょっとね……」
そこまで言われて、女心の機微に疎いヤマダくんもようやく事情を察した。
妻も、タバタさんも、世間では“アラサー”とひとくくりにされるお年頃だ。学生時代からの親友とはいえ、アラサー女性同士で一方が独身、一方が既婚者となると、やはり、お互いに気を遣うことが多くなる。それでも、引っ越す前までは、ひとつ屋根の下で暮らしていたからそれなりに交流もあったが、妻が『バーデン-S』に転居したことで、その接点もなくなった。どちらが悪いということでもないのだが、何となく疎遠になってしまったのだろう。
「――わかった。じゃあ、今回は俺ひとりで向こうのパーティに参加するよ」
ものわかりのいい夫、というつもりでそう言ったヤマダくんだったが、妻はさらに追い打ちをかけてくる。
「こっちのパーティはどうするの?」
言われて、ヤマダくんは今さらのようにはっとした。『バーデン-S』は『バーデン-S』で、クリスマスパーティを開くことになる。イシザキ家のソウタくんはともかく、アオノ家のノゾミちゃんはもう1歳9ヶ月、離乳食でなくてもいろいろなものが食べられるようになってきた。今年は事実上初めてのクリスマスパーティということで、ずいぶんと楽しみにしているようだった。
大人たちにとっても、この『バーデン-S』で迎える初めてのクリスマスだ。アオノ夫人が中心になり、3家族の奥様はいろいろと準備を考えていたようである。
「問題は日程だな。今年の24日・25日は平日のド真ン中だし、23日も祝日じゃないから、たぶん、その前の週末か、次の週末になるか……」
脳裏にカレンダーを思い浮かべながら、ヤマダくんがつぶやく。
「あらかじめ言っとくけど、うちのクリスマスは21日だよ?」
妻はドライな口調で言った。
「――で。もし、同じ日だったらどうするつもり?」
ヤマダくんは観念したように答えた。
「…………どっちも出るよ」
そして、ヤマダくんは12月21日を迎える――『バーデン-H』で。
――さっきから、ヤマダくんはしきりにスマホの画面を覗き込んでいた。小さな画面の中では、テレビ電話を通じて『バーデン-S』のリビングの現在のようすが映像で流れていた。最初のうちは、こちら側でもパーティのようすを撮影していたのだが、今はカメラを切り替えて、ヤマダくん自身の顔だけが映っている状態だった。
まもなく午後8時になる。こちらのパーティは、まさに宴もたけなわであった。
と――ふいに、小さな人影がカメラに向かってよたよたと近寄ってきた。
「やまだのおじちゃん、おやしゅみなさい」
画面いっぱいにアップになったノゾミちゃんの顔が、眠そうな声で言う。
「はやくかえってきてね。ばりーもまってるよ」
「うん。おやすみ」
なんだか泣きそうな気分になりながら、ヤマダくんはかろうじてそう返事をした。
ノゾミちゃんの顔が引っ込むと、代わって画面にアップになったのはヤマダくんの妻だった。
「そっちはどう? 楽しんでる?」
「……まあね」
いささか気まずい思いで、ヤマダくんは短く応じた。さぞかし怒っているに違いない――そう思っていたヤマダくんだったが、妻の口調は意外なほどに穏やかだった。
「――気をつけて帰ってきてね。待ってるから……」
その、妻の言葉を聞いて――。
弾かれたように腰を上げると、あわただしく帰り支度をはじめるヤマダくんだった。
(つづく)
「メリークリスマ〜ス!!」
司会者の音頭に合わせて、テーブルを囲んで居並ぶ10人ほどのメンバーがいっせいに唱和する。めいめいが好みの飲み物を満たしたグラスを掲げ、周りの者たちのグラスに次々に合わせる。カチン、チン、チン……と澄んだ音がそこかしこで響いた。
そのようすを見渡しながら、ヤマダくんは心の中でかすかな寂しさを感じていた。
(――やっぱり、去年までと比べると今年はちょっと、な……)
1年前のクリスマスパーティは、じつに華やかに盛り上がった。2年前はごく普通のパーティだったが、3年前には人数が今の倍近くいて、リビングに収まり切れないほどだった。それらに比べてしまうと、参加人数からしても、今年はややこぢんまりとした感が強い。
(…………まあ、それもしょうがないか)
1年前のクリスマスは、ちょうど、その直前に急遽決まったヤマダくんと、当時は婚約者であったワタナベさんとの挙式の前祝い、という意味合いもあって、頭数は同じくらいでも、個々のメンバーのテンションが異常なくらい高かった。また、3年前には、当時ヤマダくんが所有していた2軒目のシェアハウス『バーデン-K』との合同パーティという形にしたため、この『バーデン-H』の入居者以外のゲスト参加が多かった。
それに対して、今年は基本的に入居者のみの参加であり、むしろ、オーナーとして参加したヤマダくん自身が唯一のゲスト枠である。去年のパーティではヤマダくんの隣にいた妻は、今ごろ、ここから電車で7駅ほど離れた『バーデン-S』で、シェアメイトたちと一緒に夫の帰りを待っていることだろう。
(――やっぱり、今年も合同パーティにしちゃえばよかったかな?)
正直、そう思わないでもなかったが――どちらを会場にするにしても、ドアツードアで片道45分以上の距離の移動は、お互い負担が大きい。かといって、双方の中間くらいの地点にパーティ会場を借りる、というのも、それはそれで趣旨が違うような気がする。なんだかんだ言っても、年に一度のクリスマスパーティなのだから、気の置けない者同士が、“我が家”で騒ぐのが一番だろう。
テーブルの上には、チキンやフライドポテト、キッシュやチーズの盛り合わせなどの皿が所狭しと並んでいる。今年はシャンパンの用意はなかったが、ワインクーラーにはよく冷えた白ワインが3本。キッチンの冷蔵庫には缶ビールや日本酒も控えている。クリスマスらしい飾りつけとしては、玄関とリビングの壁にクリスマスモールが架けられていた。
「――ヤマダさ〜ん、飲んでますか〜?」
そう言いながらワインのボトルを構える101号室のイトウくん――現・シェアメイトリーダーであり、今年のパーティの主催者――に、まだ半分ほど残っている自分のグラスを突き出しながら、ヤマダくんは、何となくアウェー感を覚えずにはいられなかった。
――話は2週間ほど前にさかのぼる。
その日、ヤマダくんは、イトウくんからの“定例報告”の電話を受けていた。
『バーデン-H』のシェアメイトリーダーであるイトウくんは、ハウスや住人たちのようすについて、毎月第1土曜日と第3土曜日の夜に電話で報告してくることになっていた。もともとは、月1回ペースでヤマダくんが『バーデン-H』まで顔を出すことにしていたのだが、いつの間にやら月2回の電話報告で済ませるようになったのである。ヤマダくんとしては、そろそろ電話も月1回でいいか、と考え始めていた。
「――そういえば、今年のクリスマスはどうします?」
そのイトウくんの言葉で、ヤマダくんはようやく、今年ももうそんな時期かと思い至った。
「どうするって……?」
怪訝そうに訊き返すヤマダくんに、
「ヤマダさんたちも参加されますよね?」
さも当たり前のことのようにイトウくんは言う。実際、彼にとっては当たり前なのだろう。ヤマダくんたちが『バーデン-S』へ引っ越してから、まだ1年とは経っていない。もともとオーナーなのだし、引っ越したといっても参加資格は十分にある。というより、ここ数ヶ月、こちらへ顔を出していないのだから、クリスマスくらいは顔を見せるべきだろう、と考えているようだった。
少し考えてから、ヤマダくんは答えた。
「――とりあえず、俺は参加させてもらうよ。他の者は、こちらで話し合ってから返事をする。ほら、まだ小さい子もいるし……」
「わかりました、お返事待ってます。ワタナ……いえ、奥さんも、来られるようでしたら、ぜひご一緒に」
うっかり旧姓で呼びそうになったのをあわてて訂正しつつ、イトウくんはそう言って電話を切った。
「……あ、」
通話の切れたスマホを見つめていたヤマダくんが、ふと、何かに気づいたように声を漏らした。
(パーティの日程、聞くの忘れてた…………ま、いっか)
「ん。わたしは遠慮しとく」
即答だった。
「あなただけ、行ってらっしゃいよ。みんなにもよろしく」
妻の返事はある意味、ヤマダくんの予想通りだった。彼女の意識としては、もう『バーデン-H』は“よそさまの家”なのだろう。この『バーデン-S』こそが我が家であり、よその家のクリスマスパーティに顔を出すのは気が進まないということのようだった。
「いや、でも、タバタさんとかもいるわけだし……」
ヤマダくんは、念の為、というつもりで妻の旧友の名前を挙げた。203号室のタバタさんは妻の学生時代からの親友であり、もとはと言えば妻の誘いで『バーデン-H』に入居した、という経緯がある。
「うーん……何て言うかな? オンナはいろいろと面倒くさいのよ」
口頭ではあったが、「オンナ」とカタカナで発音したニュアンスが伝わってくる。いつにない妻の生々しい声音に、ヤマダくんはちょっとドギマギする。
「わたしが結婚しちゃったから、ちょっとね……」
そこまで言われて、女心の機微に疎いヤマダくんもようやく事情を察した。
妻も、タバタさんも、世間では“アラサー”とひとくくりにされるお年頃だ。学生時代からの親友とはいえ、アラサー女性同士で一方が独身、一方が既婚者となると、やはり、お互いに気を遣うことが多くなる。それでも、引っ越す前までは、ひとつ屋根の下で暮らしていたからそれなりに交流もあったが、妻が『バーデン-S』に転居したことで、その接点もなくなった。どちらが悪いということでもないのだが、何となく疎遠になってしまったのだろう。
「――わかった。じゃあ、今回は俺ひとりで向こうのパーティに参加するよ」
ものわかりのいい夫、というつもりでそう言ったヤマダくんだったが、妻はさらに追い打ちをかけてくる。
「こっちのパーティはどうするの?」
言われて、ヤマダくんは今さらのようにはっとした。『バーデン-S』は『バーデン-S』で、クリスマスパーティを開くことになる。イシザキ家のソウタくんはともかく、アオノ家のノゾミちゃんはもう1歳9ヶ月、離乳食でなくてもいろいろなものが食べられるようになってきた。今年は事実上初めてのクリスマスパーティということで、ずいぶんと楽しみにしているようだった。
大人たちにとっても、この『バーデン-S』で迎える初めてのクリスマスだ。アオノ夫人が中心になり、3家族の奥様はいろいろと準備を考えていたようである。
「問題は日程だな。今年の24日・25日は平日のド真ン中だし、23日も祝日じゃないから、たぶん、その前の週末か、次の週末になるか……」
脳裏にカレンダーを思い浮かべながら、ヤマダくんがつぶやく。
「あらかじめ言っとくけど、うちのクリスマスは21日だよ?」
妻はドライな口調で言った。
「――で。もし、同じ日だったらどうするつもり?」
ヤマダくんは観念したように答えた。
「…………どっちも出るよ」
そして、ヤマダくんは12月21日を迎える――『バーデン-H』で。
――さっきから、ヤマダくんはしきりにスマホの画面を覗き込んでいた。小さな画面の中では、テレビ電話を通じて『バーデン-S』のリビングの現在のようすが映像で流れていた。最初のうちは、こちら側でもパーティのようすを撮影していたのだが、今はカメラを切り替えて、ヤマダくん自身の顔だけが映っている状態だった。
まもなく午後8時になる。こちらのパーティは、まさに宴もたけなわであった。
と――ふいに、小さな人影がカメラに向かってよたよたと近寄ってきた。
「やまだのおじちゃん、おやしゅみなさい」
画面いっぱいにアップになったノゾミちゃんの顔が、眠そうな声で言う。
「はやくかえってきてね。ばりーもまってるよ」
「うん。おやすみ」
なんだか泣きそうな気分になりながら、ヤマダくんはかろうじてそう返事をした。
ノゾミちゃんの顔が引っ込むと、代わって画面にアップになったのはヤマダくんの妻だった。
「そっちはどう? 楽しんでる?」
「……まあね」
いささか気まずい思いで、ヤマダくんは短く応じた。さぞかし怒っているに違いない――そう思っていたヤマダくんだったが、妻の口調は意外なほどに穏やかだった。
「――気をつけて帰ってきてね。待ってるから……」
その、妻の言葉を聞いて――。
弾かれたように腰を上げると、あわただしく帰り支度をはじめるヤマダくんだった。
(つづく)
シェアハウス大家さん倶楽部について
新着コンテンツ
-
第144回 2026年とシェアハウス
2026-1-15 -
第143回 変化の時代とシェアハウス
2025-12-19 -
第142回 光明とシェアハウス
2025-11-17 -
第141回 抵抗感とシェアハウス
2025-10-16 -
第140回 未来予想図とシェアハウス
2025-9-16 -
第139回 不動産市況とシェアハウス2025夏
2025-8-16 -
第138回 公的支援とシェアハウス
2025-7-15 -
第137回 変わらぬ魅力とシェアハウス
2025-6-16 -
第136回 「不都合な真実」とシェアハウス
2025-5-16 -
第135回 時の流れとシェアハウス
2025-4-17
〜シェアハウス事業を企画から運営まで、トータルにサポート〜
運営会社:株式会社シェアスタイル | シェアハウス資産運用のご相談はこちら | シェアハウス管理物件のご紹介はこちら | 採用情報
Copyright © 2006-2015 ShareStyle Co.,Ltd. All Rights Reserved.