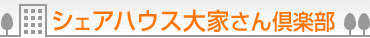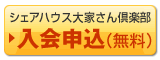第82話 ヤマダくん、緊急事態!?
――開かれたカーテンの間から、朝のまぶしい光が寝室に差し込んでくる。ベッドの上で身じろぎしつつ、なおも未練がましく掛け布団をかぶろうとするヤマダくんに、彼の愛妻が声をかけてきた。
「おはよう。もう7時過ぎだよ」
すっかり聞き慣れた穏やかな声音であったが、どこか、あきれたような響きが語尾に混じっていた。それもそのはず――つい昨日までは、とっくに朝食を済ませて玄関から出て行こうかという時間帯であった。
「…………おはよ」
もごもごと口の中でつぶやき、ヤマダくんは昨夜ベッドサイドに置いたはずのメガネをまさぐる。が、予想していた感触は手に当たらず、むなしく周囲をうろうろするばかりだ。
「――ほら、」
今度こそあきれた声で、妻が空をさまよう手にメガネを押しつける。手さぐりで受け取って、頭を枕に押しつけたままの恰好で顔にメガネを載せる。それでようやく瞼を開けたヤマダくんだったが、寝起きの視界は一向に霞が晴れない。
「…………?」
反射的にまばたきしたヤマダくんは、違和感の理由を悟って苦笑する。起きたばかりの目ヤニに加えて、レンズに指紋がベタベタついていたからだ。昨日、予想もしていなかった“とある事態”に巻き込まれ、ベッドに入るのが遅くなったせいもある。――とはいえ、それでようやく、ヤマダくんは本格的に覚醒に至ったようだ。
勢いよく、がばっと上体を起こすと、あいかわらず動きの鈍い舌でつぶやく。
「7時……?」
いつもの起床時間より1時間半以上遅い。休日でなければ確実に遅刻だ。だが――。
「……………ああ、そっか」
心地よい寝床から這い出しながら、ヤマダくんは得心したようにひとりごちた。
「……当分、朝はこの時間でいいんだっけ――」
――かれこれ1ヶ月以上前。
新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、ヤマダくんの勤務する会社でも時差通勤制度が導入された。都心にオフィスを構える会社の中でも、その判断は比較的早い方だったと思う。ただし、その時点ではあくまで「時差通勤」、いわゆる「オフピーク通勤」の範囲にとどまっており、「満員電車は避けて通勤せよ」というレベルで、ヤマダくんたちはあいかわらず会社へは毎日出勤することが求められていた。それも無理のない話で、一部上場の大企業であればともかく、ヤマダくんたちの会社程度の中堅企業では、まだまだテレワークなど現実的な選択肢ではなかったからだ。社員が在宅で仕事ができるだけの環境整備も追いついていなかったし、勤怠管理の問題もあった。
だが、そうこうしているうちに、4月7日を迎え――東京をはじめとする7都府県に「緊急事態宣言」が発令された。もはや、待ったなしの状況だった。
幸い――というべきだろう。ヤマダくんたちの会社は、かろうじて都の求める「自粛」を実践できるだけの体力があった。といっても、おそらくギリギリというところだろう。各部署にひとりふたりいた派遣社員は3月いっぱいで契約を打ち切られたし――もともと、契約更新時期でもあったが――ヤマダくんたち正社員にしても、一斉に在宅勤務に入れるだけのリソースはまだ社内にはなかった。
そこで、3月上旬から試験的に開始していた交替での在宅勤務枠を段階的に拡大し、可能な限り全社員がテレワーク体制に移行できるように準備が進められていった。そうして、4月14日の火曜日を迎えたのである。
その日は、ヤマダくんにとって在宅勤務前の最後の出勤日であった。同じ会社の隣の部署の配属であるヤマダ夫人は、ひと足早く先週末から在宅勤務に入っていた。
前日の大雨が嘘のように空はカラリと晴れ上がっていたが、強い風が吹きつけて肌寒さを感じる一日だった。駅までの道中は、すれ違う人影もまばらだったが、誰もが一様にマスクを着用していた。使い捨てマスクの入手困難からか、近頃では手縫いのマスクを着けている者も少なくない。
今やガラガラに空いた通勤電車に揺られながら、在庫が残り少なくなってきたマスク――本来は使い捨てだが、マスクの内側に小さく切ったキッチンペーパーを挟むといういじましい手段で数日間使いまわしていた――に身を固めて、ヤマダくんは不安気に車内を見渡していた。もちろん、何も見えはしないのだが、そこらの空気中にウィルスが漂っているかもしれないと思えば、うっかり呼吸することも憚られるようだった。
会社に着くと、真っ先にトイレに駆け込んで入念に手を洗う。いささか神経質になり過ぎていると思わないでもなかったが、無神経よりは何百倍もマシだと思うことにした。
彼のほかには2、3人しか見かけない同僚たちとも、お互いに離れて声をかけ合うにとどめ、多少込み入った話は同じオフィス内にいてもわざわざスマホを通じてやりとりする。まったく、異常な光景だ。そう思っていても、そうせずにはいられなかった。
在宅勤務に必要な機材――といっても、貸し出し可のノートパソコン等はとっくに出払っているので、ヤマダくんも含めて大多数は自前で賄っている――や、持ち出し可能な資料を手早くまとめ、彼の権限でアクセス可能な会社のクラウド上の資料等については念の為パスワードをもう一度確認しておく。これで一応、準備は完了だ。
(――とはいえ、ホントに在宅で大丈夫なのかね……?)
ヤマダくん直通の電話はスマホに転送されるようになっているが、完全に社内にいるときと同じ対応ができるという自信はなかった。もっとも、主だった取引先にしても事情は同様だろう。会社の機能としては間違いなく半分以下に低下するだろうが、何の補償の確約もなく休業を要請されるよりははるかにマシなはずだった。
(……今期の業績も赤字は免れないだろうが、さすがにすぐ倒産するってことは――)
ない、とは必ずしも言い切れないのが今の状況だったが、それは考えても仕方がない。ヤマダくんも本質的には楽天家なのだ。
(そうなったら――そのときはそのときさ)
これ以上会社にいても、気が滅入るばかりだ。そう考えて、ヤマダくんは荷物を抱えて早々に退社することにした。
ちょうど、昼どきだった。
オフィス街は閑散としていたが、そのせいで営業している店も少なく、わずかに店を開けているところは、逆にどこも混雑していた。今や自粛ムード一色の都心のオフィス街で、どこから湧いてきたのかと思うほどの人数に少々うんざりする。彼らにしても、営業している店が少ないから選択の余地がないのだろうが……。
このご時世、不特定多数との濃厚接触だけは御免こうむりたいヤマダくんは、昼食をあきらめて駅に足を向けたのだが――ふと思い立って、いつも通勤に使っているのとは違う路線に乗り込むことにする。時間帯のせいもあって、こちらの電車もガラガラだ。数駅で乗り換え、ヤマダくんが降り立ったのは、年末以来数ヶ月ぶりに訪れるH‐駅だった。
駅前のファミレス――ここはかつて、ヤマダくんがさまざまな顔ぶれとともに立ち寄り、いくつかのささやかなドラマが演じられた舞台でもあった――は店を開けていたので、ここで昼食を摂ることにする。注文を済ませたヤマダくんは、ちょっと考えた末、スマホである番号をコールする。
ヤマダくんの所有する1軒目のシェアハウス『バーデン-H』の固定電話だった。
呼び出し音数回の間で、予想通り相手が出た。
「……はい? こちら『バーデン-H』――」
「ヤマダです。……イトウくん? よかった、やっぱそっちにいたか」
「え、ヤマダさんですか?」
驚いた反応は、間違いなく『バーデン-H』の現在のシェアメイトリーダーを任せているイトウくんだ。1週間前に緊急事態宣言が出た夜、電話で話したときには何も言っていなかったが、どうやら彼も今日は出勤してはいないらしい。
「――近くまで来ているんだ。こっちへは当分来られそうもないから、ちょっと顔を出そうかと思って……」
そう言いかけたヤマダくんを――。
「待った! ――今来ちゃダメです!!」
予想外に鋭い声音で、イトウくんが遮ったのだった。
(つづく)
「おはよう。もう7時過ぎだよ」
すっかり聞き慣れた穏やかな声音であったが、どこか、あきれたような響きが語尾に混じっていた。それもそのはず――つい昨日までは、とっくに朝食を済ませて玄関から出て行こうかという時間帯であった。
「…………おはよ」
もごもごと口の中でつぶやき、ヤマダくんは昨夜ベッドサイドに置いたはずのメガネをまさぐる。が、予想していた感触は手に当たらず、むなしく周囲をうろうろするばかりだ。
「――ほら、」
今度こそあきれた声で、妻が空をさまよう手にメガネを押しつける。手さぐりで受け取って、頭を枕に押しつけたままの恰好で顔にメガネを載せる。それでようやく瞼を開けたヤマダくんだったが、寝起きの視界は一向に霞が晴れない。
「…………?」
反射的にまばたきしたヤマダくんは、違和感の理由を悟って苦笑する。起きたばかりの目ヤニに加えて、レンズに指紋がベタベタついていたからだ。昨日、予想もしていなかった“とある事態”に巻き込まれ、ベッドに入るのが遅くなったせいもある。――とはいえ、それでようやく、ヤマダくんは本格的に覚醒に至ったようだ。
勢いよく、がばっと上体を起こすと、あいかわらず動きの鈍い舌でつぶやく。
「7時……?」
いつもの起床時間より1時間半以上遅い。休日でなければ確実に遅刻だ。だが――。
「……………ああ、そっか」
心地よい寝床から這い出しながら、ヤマダくんは得心したようにひとりごちた。
「……当分、朝はこの時間でいいんだっけ――」
――かれこれ1ヶ月以上前。
新型コロナウィルスの感染拡大を受けて、ヤマダくんの勤務する会社でも時差通勤制度が導入された。都心にオフィスを構える会社の中でも、その判断は比較的早い方だったと思う。ただし、その時点ではあくまで「時差通勤」、いわゆる「オフピーク通勤」の範囲にとどまっており、「満員電車は避けて通勤せよ」というレベルで、ヤマダくんたちはあいかわらず会社へは毎日出勤することが求められていた。それも無理のない話で、一部上場の大企業であればともかく、ヤマダくんたちの会社程度の中堅企業では、まだまだテレワークなど現実的な選択肢ではなかったからだ。社員が在宅で仕事ができるだけの環境整備も追いついていなかったし、勤怠管理の問題もあった。
だが、そうこうしているうちに、4月7日を迎え――東京をはじめとする7都府県に「緊急事態宣言」が発令された。もはや、待ったなしの状況だった。
幸い――というべきだろう。ヤマダくんたちの会社は、かろうじて都の求める「自粛」を実践できるだけの体力があった。といっても、おそらくギリギリというところだろう。各部署にひとりふたりいた派遣社員は3月いっぱいで契約を打ち切られたし――もともと、契約更新時期でもあったが――ヤマダくんたち正社員にしても、一斉に在宅勤務に入れるだけのリソースはまだ社内にはなかった。
そこで、3月上旬から試験的に開始していた交替での在宅勤務枠を段階的に拡大し、可能な限り全社員がテレワーク体制に移行できるように準備が進められていった。そうして、4月14日の火曜日を迎えたのである。
その日は、ヤマダくんにとって在宅勤務前の最後の出勤日であった。同じ会社の隣の部署の配属であるヤマダ夫人は、ひと足早く先週末から在宅勤務に入っていた。
前日の大雨が嘘のように空はカラリと晴れ上がっていたが、強い風が吹きつけて肌寒さを感じる一日だった。駅までの道中は、すれ違う人影もまばらだったが、誰もが一様にマスクを着用していた。使い捨てマスクの入手困難からか、近頃では手縫いのマスクを着けている者も少なくない。
今やガラガラに空いた通勤電車に揺られながら、在庫が残り少なくなってきたマスク――本来は使い捨てだが、マスクの内側に小さく切ったキッチンペーパーを挟むといういじましい手段で数日間使いまわしていた――に身を固めて、ヤマダくんは不安気に車内を見渡していた。もちろん、何も見えはしないのだが、そこらの空気中にウィルスが漂っているかもしれないと思えば、うっかり呼吸することも憚られるようだった。
会社に着くと、真っ先にトイレに駆け込んで入念に手を洗う。いささか神経質になり過ぎていると思わないでもなかったが、無神経よりは何百倍もマシだと思うことにした。
彼のほかには2、3人しか見かけない同僚たちとも、お互いに離れて声をかけ合うにとどめ、多少込み入った話は同じオフィス内にいてもわざわざスマホを通じてやりとりする。まったく、異常な光景だ。そう思っていても、そうせずにはいられなかった。
在宅勤務に必要な機材――といっても、貸し出し可のノートパソコン等はとっくに出払っているので、ヤマダくんも含めて大多数は自前で賄っている――や、持ち出し可能な資料を手早くまとめ、彼の権限でアクセス可能な会社のクラウド上の資料等については念の為パスワードをもう一度確認しておく。これで一応、準備は完了だ。
(――とはいえ、ホントに在宅で大丈夫なのかね……?)
ヤマダくん直通の電話はスマホに転送されるようになっているが、完全に社内にいるときと同じ対応ができるという自信はなかった。もっとも、主だった取引先にしても事情は同様だろう。会社の機能としては間違いなく半分以下に低下するだろうが、何の補償の確約もなく休業を要請されるよりははるかにマシなはずだった。
(……今期の業績も赤字は免れないだろうが、さすがにすぐ倒産するってことは――)
ない、とは必ずしも言い切れないのが今の状況だったが、それは考えても仕方がない。ヤマダくんも本質的には楽天家なのだ。
(そうなったら――そのときはそのときさ)
これ以上会社にいても、気が滅入るばかりだ。そう考えて、ヤマダくんは荷物を抱えて早々に退社することにした。
ちょうど、昼どきだった。
オフィス街は閑散としていたが、そのせいで営業している店も少なく、わずかに店を開けているところは、逆にどこも混雑していた。今や自粛ムード一色の都心のオフィス街で、どこから湧いてきたのかと思うほどの人数に少々うんざりする。彼らにしても、営業している店が少ないから選択の余地がないのだろうが……。
このご時世、不特定多数との濃厚接触だけは御免こうむりたいヤマダくんは、昼食をあきらめて駅に足を向けたのだが――ふと思い立って、いつも通勤に使っているのとは違う路線に乗り込むことにする。時間帯のせいもあって、こちらの電車もガラガラだ。数駅で乗り換え、ヤマダくんが降り立ったのは、年末以来数ヶ月ぶりに訪れるH‐駅だった。
駅前のファミレス――ここはかつて、ヤマダくんがさまざまな顔ぶれとともに立ち寄り、いくつかのささやかなドラマが演じられた舞台でもあった――は店を開けていたので、ここで昼食を摂ることにする。注文を済ませたヤマダくんは、ちょっと考えた末、スマホである番号をコールする。
ヤマダくんの所有する1軒目のシェアハウス『バーデン-H』の固定電話だった。
呼び出し音数回の間で、予想通り相手が出た。
「……はい? こちら『バーデン-H』――」
「ヤマダです。……イトウくん? よかった、やっぱそっちにいたか」
「え、ヤマダさんですか?」
驚いた反応は、間違いなく『バーデン-H』の現在のシェアメイトリーダーを任せているイトウくんだ。1週間前に緊急事態宣言が出た夜、電話で話したときには何も言っていなかったが、どうやら彼も今日は出勤してはいないらしい。
「――近くまで来ているんだ。こっちへは当分来られそうもないから、ちょっと顔を出そうかと思って……」
そう言いかけたヤマダくんを――。
「待った! ――今来ちゃダメです!!」
予想外に鋭い声音で、イトウくんが遮ったのだった。
(つづく)
シェアハウス大家さん倶楽部について
新着コンテンツ
-
第123回 ライフステージとシェアハウス
2024-4-16 -
第122回 景気回復とシェアハウス2024
2024-3-15 -
第121回 生活困窮者とシェアハウス
2024-2-15 -
第120回 震災とシェアハウス2024
2024-1-15 -
第119回 プレスリリースとシェアハウスその2
2023-12-15 -
第118回 住宅難とシェアハウス
2023-11-30 -
第117回 プレスリリースとシェアハウス
2023-10-15 -
第116回 アンケート調査とシェアハウス
2023-9-15 -
第115回 防災とシェアハウス
2023-8-15 -
第114回 猛暑とシェアハウス
2023-7-15
〜シェアハウス事業を企画から運営まで、トータルにサポート〜
運営会社:株式会社シェアスタイル | シェアハウス資産運用のご相談はこちら | シェアハウス管理物件のご紹介はこちら | 採用情報
Copyright © 2006-2015 ShareStyle Co.,Ltd. All Rights Reserved.