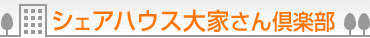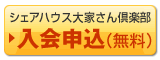第85話 ヤマダくん、頭を下げる
「お疲れさまっス!」
「お疲れー」
「お疲れさまでした」
「お先に失礼しまーす」
口々に辞去の挨拶を投げかけつつ、モニタ上に開いていた小画面が次々と閉じていく。あっという間に誰もいなくなったのを確認して、ヤマダくんも「退室する」をクリックした。本日のオンラインミーティング、無事終了だ。
その気配を察したらしく、ドアに遠慮がちなノックの音がした。
「……入っていい?」
「ああ、どうぞ――」
ヤマダくんの返事と同時に、ドアを開けて入ってきたのは彼の妻だ。手にした小ぶりのおぼんには、よく冷えた麦茶を満たしたコップが載っていた。そのコップを差し出しながら、妻はヤマダくんの労をねぎらう。
「お疲れさま。ひと息入れたら――?」
「うん、そうしたいのはヤマヤマなんだけどね……」
一瞬ためらった後、ヤマダくんは自分に言い聞かせるように答えた。
「記憶が薄れないうちに、今の議事録まとめて課長と共有しておかないと……」
これがオフィスだったら――と、ついつい詮ないことを考えてしまうヤマダくんだった――課長にはせいぜい、口頭で二言みこと報告するだけでよかった。正式な議事録が必要になる場合は、部下に作成させることもできた。それが、現状では、主任であるヤマダくん自身が簡略な議事録をまとめて課長にメールする、という手間をかけなければならなくなっていたのである。もっとも、特に社内ルールとして定められているわけでなく、あくまで慣習ではあったが。
「……たいへんね」
心配そうな妻の口調に、ヤマダくんは敢えて空元気を出してみせた。
「慣れりゃどうってことないって。それに、やってみたら案外うまくいくもんだよ」
2020年8月のお盆休み明け――今年は何もかもイレギュラーづくめで、お盆休みも全社一斉にではなく、分散しての休暇取得となったが、それでも山の日から終戦記念日と絡めた前後に休む者がいちばん多かった。
なお、ヤマダくんの会社は7月1日から「基本的には通常出社、希望者のみ在宅勤務」という体制で、当初は出社してくる者も少なくなかったが、東京都の感染再拡大のニュースを受けて出社メンバーは一気に激減。今では、東京本社オフィスの出社率は10%未満というところだろう。一応、管理職のはしくれであるヤマダくんは、同僚たちよりは出社機会が多かったが、それでも7月下旬にふたたび自由出社となってからは、週に1日出るかどうかというくらいに減らしていた。今日も在宅勤務にさせてもらい、お盆休み明けの今週は出社予定がなかった。
Word文書でA4用紙1枚程度、覚書の議事録をまとめ、直属の上司である課長宛てにメール添付で送信。これでようやくひと段落だ。
妻の持ってきてくれた麦茶の残り――すでに生ぬるくなりかけていたが――を、ひと息に飲み干す。やれやれ、と声に出さずにひとりごちて、ヤマダくんはそこで初めて背後に向き直った。
閉ざされたドアの向こうで、かすかな話し声が漏れ聞こえてくる。一人は彼の妻だが、話している相手の声はくぐもってよく聴き取れない。どうやら、妻は妻でオンラインの相手と対話中のようだ。ヤマダくんに飲み物を持ってきてくれた後、彼女も仕事に戻ったらしい。
「―――――やれやれ」
今度はわざとらしく声に出してヤマダくんがつぶやく。同じ会社に勤めているとはいえ、彼と妻とは所属部署が違う。当然、仕事と休憩のタイミングは噛み合わない。一つ屋根の下で、同じ会社の仕事をしていながら、勤務時間中は自由に私語を交わすこともままならないのだ。まあ、それは二人とも出勤していても同じことなのだが。
ちらりとパソコン画面の時刻表示を見て、まだまだ勤務時間がたっぷり残っていることを確かめると、ヤマダくんは空のコップを手に立ちあがった。キッチンの冷蔵庫に飲み物の追加を取りに行きがてら、途中、リビングのテーブルでノートパソコンに向き合っている妻の背中を見やり――ヤマダくんはふたたび意識を仕事モードに切り替えた。
「――お疲れさま」
数時間後、その日の仕事に区切りをつけると、ヤマダくん夫妻はどちらからともなく声をかけあった。妻の顔にはだいぶ疲労の色が濃い。すでに妊娠8ヶ月目に入った下腹部は大きくせりだし、座ったり立ったりするだけでもしんどそうだ。
「晩ご飯……」
と言いかけた妻に、
「あ、いい。今日はおれがやるよ」
ヤマダくんは被せるように言った。
「大丈夫? 食欲ある……?」
つわりの時期はもう終わっていたが、このところの猛暑続きもあって、妻の食がすっかり細くなっていることをヤマダくんは気にしていた。
「うん………少しなら……」
ためらいがちに妻が答える。しっかり栄養を摂らなければならない時期なのは承知していたが、あいにくヤマダくんの料理のレパートリーはそれほど多くない。冷蔵庫の野菜室を覗き込んで、在庫を確かめると、ナスの残りとピーマンが2、3個しかない。
「昨夜と同じになっちゃうけど……」
言いにくそうにヤマダくんがおずおずと口にする。この食材で彼にできる料理は、昨夜もつくった豚肉の炒め物くらいだ。
「ううん、平気」
妻は気にも止めないように答えるが、それはそれでヤマダくんの気が咎める。
「ちょっと待ってな。今、何か適当にレシピを――」
スマホを手に取って、ヤマダくんは何か別の調理法がないか、ネットで調べようとする。そこへ――。
「――こんばんは!」
場違いに元気のいい声が、ヤマダ家のリビングに続くドアの向こう側からかけられた。
「? ノゾミちゃん?」
声の主は聞き間違えようもない、『バーデン⁻S』の同居人の一人、アオノ家の長女ノゾミちゃんだった。
あわててドアを手前に引くと、ノゾミちゃんの後ろでにこにこしているアオノ夫人の姿が目に飛び込んできた。
「え? どうしたんですか?」
予想外のことに驚くヤマダくんに、アオノ夫人はにっこり笑って、持っていた両手鍋をかるくもたげて見せた。
「こんばんは。つくりすぎちゃったからおすそ分けにと思って……」
「おねえさん――」
その会話を聞いて、ソファでぐったりへたり込んでいたヤマダくんの妻が、驚いたように顔を上げる。
「おととい、買い物に行けなかったでしょ? 困ってるんじゃないかと」
何でもないことのようにアオノ夫人は言うが、測ったように見事なタイミングだった。これだけ在宅勤務が続けば、『バーデン⁻S』の一つ屋根の下で暮らしている以上、ヤマダ家の仕事終わりや夕食のタイミングはおおよそ把握できるだろうし、妊婦であるヤマダ夫人の体調は常に気にかけてくれている。今夜あたり、夕食の支度にも苦労するに違いないと見て、気を回してくれたようだ。
「………ありがとうございます」
恐縮しながら、ヤマダくんが鍋を受け取る。手にかかるずっしりとした重さは、アオノ夫人が込めた気持ちの重みだけでなく、鍋の内容物による物理的な重量もある。
「ところで、これ――中身は何です?」
「夏野菜たっぷりのラタトゥイユよ。お口に合うといいんだけど……」
謙遜気味にそう言うアオノ夫人だが、言い終わらぬうちにヤマダ夫人は歓声を上げる。
「わぁ……! 私、おねえさんのラタトゥイユ、大好き!!」
その言葉と、妻の明るい表情を受けて。
もう一度、心の中で頭を下げるヤマダくんだった。
(つづく)
「お疲れー」
「お疲れさまでした」
「お先に失礼しまーす」
口々に辞去の挨拶を投げかけつつ、モニタ上に開いていた小画面が次々と閉じていく。あっという間に誰もいなくなったのを確認して、ヤマダくんも「退室する」をクリックした。本日のオンラインミーティング、無事終了だ。
その気配を察したらしく、ドアに遠慮がちなノックの音がした。
「……入っていい?」
「ああ、どうぞ――」
ヤマダくんの返事と同時に、ドアを開けて入ってきたのは彼の妻だ。手にした小ぶりのおぼんには、よく冷えた麦茶を満たしたコップが載っていた。そのコップを差し出しながら、妻はヤマダくんの労をねぎらう。
「お疲れさま。ひと息入れたら――?」
「うん、そうしたいのはヤマヤマなんだけどね……」
一瞬ためらった後、ヤマダくんは自分に言い聞かせるように答えた。
「記憶が薄れないうちに、今の議事録まとめて課長と共有しておかないと……」
これがオフィスだったら――と、ついつい詮ないことを考えてしまうヤマダくんだった――課長にはせいぜい、口頭で二言みこと報告するだけでよかった。正式な議事録が必要になる場合は、部下に作成させることもできた。それが、現状では、主任であるヤマダくん自身が簡略な議事録をまとめて課長にメールする、という手間をかけなければならなくなっていたのである。もっとも、特に社内ルールとして定められているわけでなく、あくまで慣習ではあったが。
「……たいへんね」
心配そうな妻の口調に、ヤマダくんは敢えて空元気を出してみせた。
「慣れりゃどうってことないって。それに、やってみたら案外うまくいくもんだよ」
2020年8月のお盆休み明け――今年は何もかもイレギュラーづくめで、お盆休みも全社一斉にではなく、分散しての休暇取得となったが、それでも山の日から終戦記念日と絡めた前後に休む者がいちばん多かった。
なお、ヤマダくんの会社は7月1日から「基本的には通常出社、希望者のみ在宅勤務」という体制で、当初は出社してくる者も少なくなかったが、東京都の感染再拡大のニュースを受けて出社メンバーは一気に激減。今では、東京本社オフィスの出社率は10%未満というところだろう。一応、管理職のはしくれであるヤマダくんは、同僚たちよりは出社機会が多かったが、それでも7月下旬にふたたび自由出社となってからは、週に1日出るかどうかというくらいに減らしていた。今日も在宅勤務にさせてもらい、お盆休み明けの今週は出社予定がなかった。
Word文書でA4用紙1枚程度、覚書の議事録をまとめ、直属の上司である課長宛てにメール添付で送信。これでようやくひと段落だ。
妻の持ってきてくれた麦茶の残り――すでに生ぬるくなりかけていたが――を、ひと息に飲み干す。やれやれ、と声に出さずにひとりごちて、ヤマダくんはそこで初めて背後に向き直った。
閉ざされたドアの向こうで、かすかな話し声が漏れ聞こえてくる。一人は彼の妻だが、話している相手の声はくぐもってよく聴き取れない。どうやら、妻は妻でオンラインの相手と対話中のようだ。ヤマダくんに飲み物を持ってきてくれた後、彼女も仕事に戻ったらしい。
「―――――やれやれ」
今度はわざとらしく声に出してヤマダくんがつぶやく。同じ会社に勤めているとはいえ、彼と妻とは所属部署が違う。当然、仕事と休憩のタイミングは噛み合わない。一つ屋根の下で、同じ会社の仕事をしていながら、勤務時間中は自由に私語を交わすこともままならないのだ。まあ、それは二人とも出勤していても同じことなのだが。
ちらりとパソコン画面の時刻表示を見て、まだまだ勤務時間がたっぷり残っていることを確かめると、ヤマダくんは空のコップを手に立ちあがった。キッチンの冷蔵庫に飲み物の追加を取りに行きがてら、途中、リビングのテーブルでノートパソコンに向き合っている妻の背中を見やり――ヤマダくんはふたたび意識を仕事モードに切り替えた。
「――お疲れさま」
数時間後、その日の仕事に区切りをつけると、ヤマダくん夫妻はどちらからともなく声をかけあった。妻の顔にはだいぶ疲労の色が濃い。すでに妊娠8ヶ月目に入った下腹部は大きくせりだし、座ったり立ったりするだけでもしんどそうだ。
「晩ご飯……」
と言いかけた妻に、
「あ、いい。今日はおれがやるよ」
ヤマダくんは被せるように言った。
「大丈夫? 食欲ある……?」
つわりの時期はもう終わっていたが、このところの猛暑続きもあって、妻の食がすっかり細くなっていることをヤマダくんは気にしていた。
「うん………少しなら……」
ためらいがちに妻が答える。しっかり栄養を摂らなければならない時期なのは承知していたが、あいにくヤマダくんの料理のレパートリーはそれほど多くない。冷蔵庫の野菜室を覗き込んで、在庫を確かめると、ナスの残りとピーマンが2、3個しかない。
「昨夜と同じになっちゃうけど……」
言いにくそうにヤマダくんがおずおずと口にする。この食材で彼にできる料理は、昨夜もつくった豚肉の炒め物くらいだ。
「ううん、平気」
妻は気にも止めないように答えるが、それはそれでヤマダくんの気が咎める。
「ちょっと待ってな。今、何か適当にレシピを――」
スマホを手に取って、ヤマダくんは何か別の調理法がないか、ネットで調べようとする。そこへ――。
「――こんばんは!」
場違いに元気のいい声が、ヤマダ家のリビングに続くドアの向こう側からかけられた。
「? ノゾミちゃん?」
声の主は聞き間違えようもない、『バーデン⁻S』の同居人の一人、アオノ家の長女ノゾミちゃんだった。
あわててドアを手前に引くと、ノゾミちゃんの後ろでにこにこしているアオノ夫人の姿が目に飛び込んできた。
「え? どうしたんですか?」
予想外のことに驚くヤマダくんに、アオノ夫人はにっこり笑って、持っていた両手鍋をかるくもたげて見せた。
「こんばんは。つくりすぎちゃったからおすそ分けにと思って……」
「おねえさん――」
その会話を聞いて、ソファでぐったりへたり込んでいたヤマダくんの妻が、驚いたように顔を上げる。
「おととい、買い物に行けなかったでしょ? 困ってるんじゃないかと」
何でもないことのようにアオノ夫人は言うが、測ったように見事なタイミングだった。これだけ在宅勤務が続けば、『バーデン⁻S』の一つ屋根の下で暮らしている以上、ヤマダ家の仕事終わりや夕食のタイミングはおおよそ把握できるだろうし、妊婦であるヤマダ夫人の体調は常に気にかけてくれている。今夜あたり、夕食の支度にも苦労するに違いないと見て、気を回してくれたようだ。
「………ありがとうございます」
恐縮しながら、ヤマダくんが鍋を受け取る。手にかかるずっしりとした重さは、アオノ夫人が込めた気持ちの重みだけでなく、鍋の内容物による物理的な重量もある。
「ところで、これ――中身は何です?」
「夏野菜たっぷりのラタトゥイユよ。お口に合うといいんだけど……」
謙遜気味にそう言うアオノ夫人だが、言い終わらぬうちにヤマダ夫人は歓声を上げる。
「わぁ……! 私、おねえさんのラタトゥイユ、大好き!!」
その言葉と、妻の明るい表情を受けて。
もう一度、心の中で頭を下げるヤマダくんだった。
(つづく)
シェアハウス大家さん倶楽部について
新着コンテンツ
-
第144回 2026年とシェアハウス
2026-1-15 -
第143回 変化の時代とシェアハウス
2025-12-19 -
第142回 光明とシェアハウス
2025-11-17 -
第141回 抵抗感とシェアハウス
2025-10-16 -
第140回 未来予想図とシェアハウス
2025-9-16 -
第139回 不動産市況とシェアハウス2025夏
2025-8-16 -
第138回 公的支援とシェアハウス
2025-7-15 -
第137回 変わらぬ魅力とシェアハウス
2025-6-16 -
第136回 「不都合な真実」とシェアハウス
2025-5-16 -
第135回 時の流れとシェアハウス
2025-4-17
〜シェアハウス事業を企画から運営まで、トータルにサポート〜
運営会社:株式会社シェアスタイル | シェアハウス資産運用のご相談はこちら | シェアハウス管理物件のご紹介はこちら | 採用情報
Copyright © 2006-2015 ShareStyle Co.,Ltd. All Rights Reserved.