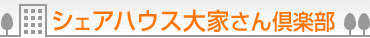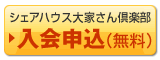第87話 ヤマダくん、パパになる!!
――枕もとで、目覚まし時計のブザーが鳴っている。
ベッドの中でもぞもぞと身動きしていたヤマダくんは、思い切って掛け布団をガバッと引きはがした。とたんに、朝の冷気が襲いかかってくる。ヌクヌクと温まっていた体温が急激に奪われていくのを感じながら、ヤマダくんはベッドから這い出した。
11月に入ると、季節が一足飛びに冬に進んだように感じられる。昨日の天気予報によれば、今日の最高気温は20度前後まで上昇するようだったが、朝夕はすでに冬の寒さだった。
「おはよう」
つぶやくようにそう声をかけた先に、妻の姿はない。代わりに、スリープモードのスマホが枕元に置かれているだけだ。つい、と手を伸ばして、ヤマダくんはスマホを起動する。待ち受け画面に、赤ん坊を抱いた母親の姿が映し出される。襁褓にくるまれた赤子は、母親の腕の中ですやすやと眠ってはいたが、両眼を閉じたその顔は安らぎに満ちているように感じられた。
我知らず、ヤマダくんの顔がほころぶ。画像の中の母親と同じ、慈愛に満ちた表情。彼にとってかけがえのないふたりの姿が、スマホの小さな画面の中にあった。
ヤマダくんの最愛の妻が出産のために入院してから、すでに3週間が過ぎていた。
その間、『バーデン⁻S』のこの寝室で寝起きしているのはヤマダくんひとりだったが、毎朝「おはよう」の声をかける習慣は、妻と寝起きしていた頃と変わらない。声をかける相手が、スマホに変わっただけだ。ただし、スマホを「起こして」から、画面に表示される画像は、ほとんど毎日のように更新されていた。
病院へ見舞いに行ったヤマダくん自身が撮影することもあれば、妻が自撮りした写真を送ってくることもある。残念ながら、ここ数日は妻の自撮り写真が多かったが、今朝はひさびさにヤマダくん自身が撮影したものだ。昨日、会社帰りに病院に立ち寄ったときの写真だった。
写真の中で妻が抱いている赤ん坊を、ヤマダくん自身はまだその手で抱かせてもらったことがない。そのせいか、父親になったという実感はまだそれほど明確ではないヤマダくんだったが、写真の中の赤ん坊が日々成長していることは、こうしてスマホを覗いているだけでも伝わってくる。心なしか、スマホを持つ手に加わってくる重みが、日一日と増していくように感じられていた。
そのままずっと画像を眺めていたいという思いを抑えて、ヤマダくんはスマホをそっと枕元に戻し、洗面所へ向かう。今朝も出勤――というより、ここ2週間は毎日、出社して仕事をしている。ヤマダくんの会社では、すでにテレワークは少数派だった。一部の企業では、コロナ禍を機にオフィスの規模を縮小して、半数以上の社員が在宅勤務を続けているところもあると聞いているが、彼の通勤するオフィスは自社ビルということもあって、大半の社員が旧来の勤務体制に戻っていた。むしろ、外部に借りていたオフィスを解約して全部署の社員を自社ビル勤務としたため、かえって通勤者数が増えているくらいだ。
手早く顔を洗い、髭を剃り、身支度を整えると、トーストとコーヒーで簡単な朝食を摂る。朝食の間に点けたテレビのニュースでは、アメリカ大統領選挙の話題で持ち切りだった。その合間にはコロナ関連のニュースも流れたものの、とりたてて耳新しい話題はない。世間は少しずつ、コロナ禍を忘れ去ろうとしているようだった。
ひとりきりの朝食を済ませ、皿を洗うと、ヤマダくんはテレビを消して立ち上がった。これから一日の仕事が始まる。だが――ヤマダくんの意識はすでに、今日も勤務終了後に立ち寄るつもりの、妻の病院へと飛んでいたのであった。
20日前――予定通り入院した妻の陣痛は、なかなか始まらなかった。ちょうど土曜日だったので、朝から付き添いで病院へ行っていたヤマダくんは、手持ちぶさたのまま昼過ぎまで病院の待合室にいたものの、同じく付き添いで来ていた妻の母親――ワタナベ夫人に追い出されてしまった。コロナ禍の影響で付き添い人数はひとりだけに制限されており、病室に入れてもらえなかったのだ。
「付き添い禁止の病院だってあるのよ。ここはまだいいほうなんだから」
言い訳めいたワタナベ夫人の言葉に、ヤマダくんは引き下がらざるをえなかった。それに、実際問題、ヤマダくんにできることは何もない。帰る前にそっと覗かせてもらった病室の妻が不安そうに見えたのが気がかりだったが、それも思い過ごしかもしれない。じつのところ、不安なのはむしろヤマダくんのほうだったのだ。
帰宅してもワタナベ夫人からは特に連絡もなく、そのまま夜になった。やがて日付が変わったが、ヤマダくんはまんじりともせずに連絡を待ち続けた。ワタナベ夫人には、陣痛が始まったらすぐに連絡してくれるように頼んでおいた。ヤマダくんは免許を持ってないが、病院までは、深夜ならタクシーを飛ばせば20分で着く。もちろん、最寄りのタクシー会社の番号はスマホに登録済みだ。すぐに家を出られるように、着替えもせず、夕食もカップ麺で簡単に済ませた。後は、スマホが鳴ったら飛び出すだけだったのだが――。
けっきょく、スマホが鳴ったのは翌朝の9時を過ぎた頃だった。飛びつくように電話に出たヤマダくんに、ワタナベ夫人はあっさりと言った。
「……産まれたわ。元気な女の子よ」
「え!?」
ヤマダくんは絶句した。陣痛が始まったらすぐに連絡してくれるようにと、昨日くどいほど念を押しておいたのに――?
電話の向こうのワタナベ夫人の声は、さすがに疲労の色がにじんでいたものの、口調はどこかのほほんとしていた。
「ごめんなさいね。……陣痛が始まったのは今朝の4時頃だったの。すぐに産室に運ばれたんだけど、こっちもバタバタしてたし、時間も時間だったから……」
ヤマダくんは脱力した。事情はわかる。もちろん、悪気などカケラもなかっただろう。それでも、妻が必死で産みの苦しみと戦っていた頃、自分は何も知らされずに家でうつらうつらとしていたのだ。産室で手を握っていられるようなご時世ではないにしろ、せめて、壁ひとつ隔てたすぐ近くにいてやりたかったのに――。
「……もしもし?」
電話の向こうの声が、ひどく遠くに感じられた。
「もしもし? 聞いてる……?」
何度か呼びかけてくるワタナベ夫人の声に、ヤマダくんはようやく気を取り直した。
「……ああ、すいません」
かろうじて、詫びの言葉が口をついて出る。自分がそばについていてやれなかった時に、妻の母親はずっと付き添ってくれていたのだ。感謝しなければならない。それに――そもそも、考えてみれば、ワタナベ夫人の時代には、夫が妻の出産に立ち会うなどということは一般的ではなかったのかもしれない。自分たちの世代とは感覚が違うのだ。
「ありがとうございました。……とにかく、これからすぐ病院へ向かいます」
そう言って、電話を切る。徹夜明けの顔は脂じみていたし、髭も伸びている。髪もべとべとだ。病院へ駆けつける前に、せめてシャワーでも浴びていくことにしよう……。
慌ただしく身支度したヤマダくんは、そのまま階下へ駆けおりようとして――ふと気づいて、隣家のドアを遠慮がちにノックする。廊下を挟んだ、アオノ家のリビングに続くドアだった。日曜日の朝らしく、ちょうど洗濯機を回す音がかすかに聞こえてくる。
「はーい」
ドアを開けてくれたのは、アオノ家の長女ノゾミちゃんだった。奥に、アオノ夫妻の姿も見える。平和な休日の朝の家族の風景がそこにあった。
「おはようございます! ……その――お陰様で」
なんと声をかけたものか、一瞬口ごもったヤマダくんだったが、そのただならぬようすを見て、聡明なアオノ夫人は察してくれたようだ。
「――産まれたのね?」
「はい!」
「……おめでとうございます」
アオノ夫妻が声を揃えて言った。ノゾミちゃんはきょとんとして両親をふり返り、それからあわてたようにぴょこん、と頭を下げてくれた。
「あ……ありがとうございます! それで、今から私――」
病院へ、と口にする前に、アオノ夫人は穏やかな口調で言った。
「――気をつけて行ってらっしゃい。イシザキさん家には私から伝えておきますから」
同じひとつ屋根の下に暮らすもうひと家族への伝言を託し、今度こそヤマダくんは『バーデン⁻S』を勢いよく飛び出した。
(つづく)
ベッドの中でもぞもぞと身動きしていたヤマダくんは、思い切って掛け布団をガバッと引きはがした。とたんに、朝の冷気が襲いかかってくる。ヌクヌクと温まっていた体温が急激に奪われていくのを感じながら、ヤマダくんはベッドから這い出した。
11月に入ると、季節が一足飛びに冬に進んだように感じられる。昨日の天気予報によれば、今日の最高気温は20度前後まで上昇するようだったが、朝夕はすでに冬の寒さだった。
「おはよう」
つぶやくようにそう声をかけた先に、妻の姿はない。代わりに、スリープモードのスマホが枕元に置かれているだけだ。つい、と手を伸ばして、ヤマダくんはスマホを起動する。待ち受け画面に、赤ん坊を抱いた母親の姿が映し出される。襁褓にくるまれた赤子は、母親の腕の中ですやすやと眠ってはいたが、両眼を閉じたその顔は安らぎに満ちているように感じられた。
我知らず、ヤマダくんの顔がほころぶ。画像の中の母親と同じ、慈愛に満ちた表情。彼にとってかけがえのないふたりの姿が、スマホの小さな画面の中にあった。
ヤマダくんの最愛の妻が出産のために入院してから、すでに3週間が過ぎていた。
その間、『バーデン⁻S』のこの寝室で寝起きしているのはヤマダくんひとりだったが、毎朝「おはよう」の声をかける習慣は、妻と寝起きしていた頃と変わらない。声をかける相手が、スマホに変わっただけだ。ただし、スマホを「起こして」から、画面に表示される画像は、ほとんど毎日のように更新されていた。
病院へ見舞いに行ったヤマダくん自身が撮影することもあれば、妻が自撮りした写真を送ってくることもある。残念ながら、ここ数日は妻の自撮り写真が多かったが、今朝はひさびさにヤマダくん自身が撮影したものだ。昨日、会社帰りに病院に立ち寄ったときの写真だった。
写真の中で妻が抱いている赤ん坊を、ヤマダくん自身はまだその手で抱かせてもらったことがない。そのせいか、父親になったという実感はまだそれほど明確ではないヤマダくんだったが、写真の中の赤ん坊が日々成長していることは、こうしてスマホを覗いているだけでも伝わってくる。心なしか、スマホを持つ手に加わってくる重みが、日一日と増していくように感じられていた。
そのままずっと画像を眺めていたいという思いを抑えて、ヤマダくんはスマホをそっと枕元に戻し、洗面所へ向かう。今朝も出勤――というより、ここ2週間は毎日、出社して仕事をしている。ヤマダくんの会社では、すでにテレワークは少数派だった。一部の企業では、コロナ禍を機にオフィスの規模を縮小して、半数以上の社員が在宅勤務を続けているところもあると聞いているが、彼の通勤するオフィスは自社ビルということもあって、大半の社員が旧来の勤務体制に戻っていた。むしろ、外部に借りていたオフィスを解約して全部署の社員を自社ビル勤務としたため、かえって通勤者数が増えているくらいだ。
手早く顔を洗い、髭を剃り、身支度を整えると、トーストとコーヒーで簡単な朝食を摂る。朝食の間に点けたテレビのニュースでは、アメリカ大統領選挙の話題で持ち切りだった。その合間にはコロナ関連のニュースも流れたものの、とりたてて耳新しい話題はない。世間は少しずつ、コロナ禍を忘れ去ろうとしているようだった。
ひとりきりの朝食を済ませ、皿を洗うと、ヤマダくんはテレビを消して立ち上がった。これから一日の仕事が始まる。だが――ヤマダくんの意識はすでに、今日も勤務終了後に立ち寄るつもりの、妻の病院へと飛んでいたのであった。
20日前――予定通り入院した妻の陣痛は、なかなか始まらなかった。ちょうど土曜日だったので、朝から付き添いで病院へ行っていたヤマダくんは、手持ちぶさたのまま昼過ぎまで病院の待合室にいたものの、同じく付き添いで来ていた妻の母親――ワタナベ夫人に追い出されてしまった。コロナ禍の影響で付き添い人数はひとりだけに制限されており、病室に入れてもらえなかったのだ。
「付き添い禁止の病院だってあるのよ。ここはまだいいほうなんだから」
言い訳めいたワタナベ夫人の言葉に、ヤマダくんは引き下がらざるをえなかった。それに、実際問題、ヤマダくんにできることは何もない。帰る前にそっと覗かせてもらった病室の妻が不安そうに見えたのが気がかりだったが、それも思い過ごしかもしれない。じつのところ、不安なのはむしろヤマダくんのほうだったのだ。
帰宅してもワタナベ夫人からは特に連絡もなく、そのまま夜になった。やがて日付が変わったが、ヤマダくんはまんじりともせずに連絡を待ち続けた。ワタナベ夫人には、陣痛が始まったらすぐに連絡してくれるように頼んでおいた。ヤマダくんは免許を持ってないが、病院までは、深夜ならタクシーを飛ばせば20分で着く。もちろん、最寄りのタクシー会社の番号はスマホに登録済みだ。すぐに家を出られるように、着替えもせず、夕食もカップ麺で簡単に済ませた。後は、スマホが鳴ったら飛び出すだけだったのだが――。
けっきょく、スマホが鳴ったのは翌朝の9時を過ぎた頃だった。飛びつくように電話に出たヤマダくんに、ワタナベ夫人はあっさりと言った。
「……産まれたわ。元気な女の子よ」
「え!?」
ヤマダくんは絶句した。陣痛が始まったらすぐに連絡してくれるようにと、昨日くどいほど念を押しておいたのに――?
電話の向こうのワタナベ夫人の声は、さすがに疲労の色がにじんでいたものの、口調はどこかのほほんとしていた。
「ごめんなさいね。……陣痛が始まったのは今朝の4時頃だったの。すぐに産室に運ばれたんだけど、こっちもバタバタしてたし、時間も時間だったから……」
ヤマダくんは脱力した。事情はわかる。もちろん、悪気などカケラもなかっただろう。それでも、妻が必死で産みの苦しみと戦っていた頃、自分は何も知らされずに家でうつらうつらとしていたのだ。産室で手を握っていられるようなご時世ではないにしろ、せめて、壁ひとつ隔てたすぐ近くにいてやりたかったのに――。
「……もしもし?」
電話の向こうの声が、ひどく遠くに感じられた。
「もしもし? 聞いてる……?」
何度か呼びかけてくるワタナベ夫人の声に、ヤマダくんはようやく気を取り直した。
「……ああ、すいません」
かろうじて、詫びの言葉が口をついて出る。自分がそばについていてやれなかった時に、妻の母親はずっと付き添ってくれていたのだ。感謝しなければならない。それに――そもそも、考えてみれば、ワタナベ夫人の時代には、夫が妻の出産に立ち会うなどということは一般的ではなかったのかもしれない。自分たちの世代とは感覚が違うのだ。
「ありがとうございました。……とにかく、これからすぐ病院へ向かいます」
そう言って、電話を切る。徹夜明けの顔は脂じみていたし、髭も伸びている。髪もべとべとだ。病院へ駆けつける前に、せめてシャワーでも浴びていくことにしよう……。
慌ただしく身支度したヤマダくんは、そのまま階下へ駆けおりようとして――ふと気づいて、隣家のドアを遠慮がちにノックする。廊下を挟んだ、アオノ家のリビングに続くドアだった。日曜日の朝らしく、ちょうど洗濯機を回す音がかすかに聞こえてくる。
「はーい」
ドアを開けてくれたのは、アオノ家の長女ノゾミちゃんだった。奥に、アオノ夫妻の姿も見える。平和な休日の朝の家族の風景がそこにあった。
「おはようございます! ……その――お陰様で」
なんと声をかけたものか、一瞬口ごもったヤマダくんだったが、そのただならぬようすを見て、聡明なアオノ夫人は察してくれたようだ。
「――産まれたのね?」
「はい!」
「……おめでとうございます」
アオノ夫妻が声を揃えて言った。ノゾミちゃんはきょとんとして両親をふり返り、それからあわてたようにぴょこん、と頭を下げてくれた。
「あ……ありがとうございます! それで、今から私――」
病院へ、と口にする前に、アオノ夫人は穏やかな口調で言った。
「――気をつけて行ってらっしゃい。イシザキさん家には私から伝えておきますから」
同じひとつ屋根の下に暮らすもうひと家族への伝言を託し、今度こそヤマダくんは『バーデン⁻S』を勢いよく飛び出した。
(つづく)
シェアハウス大家さん倶楽部について
新着コンテンツ
-
第144回 2026年とシェアハウス
2026-1-15 -
第143回 変化の時代とシェアハウス
2025-12-19 -
第142回 光明とシェアハウス
2025-11-17 -
第141回 抵抗感とシェアハウス
2025-10-16 -
第140回 未来予想図とシェアハウス
2025-9-16 -
第139回 不動産市況とシェアハウス2025夏
2025-8-16 -
第138回 公的支援とシェアハウス
2025-7-15 -
第137回 変わらぬ魅力とシェアハウス
2025-6-16 -
第136回 「不都合な真実」とシェアハウス
2025-5-16 -
第135回 時の流れとシェアハウス
2025-4-17
〜シェアハウス事業を企画から運営まで、トータルにサポート〜
運営会社:株式会社シェアスタイル | シェアハウス資産運用のご相談はこちら | シェアハウス管理物件のご紹介はこちら | 採用情報
Copyright © 2006-2015 ShareStyle Co.,Ltd. All Rights Reserved.