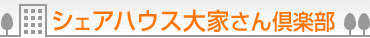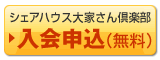第98話 ヤマダくん、その気になる!?
「またか…………」
言わでもがなのつぶやきが、無意識に漏れる。苦笑してみせる空元気さえ、湧いてこない。それどころか、文字通り、がっくりと肩を落としてさえいた。何度もくりかえされた失望の念が、いつしか絶望に取って代わったかのように、ヤマダくんは見るからにしょげかえっていた。
――ドタキャンであった。
現われるはずの相手が、約束の時間を30分以上過ぎても現れなかったのだ。電話連絡一本ない。約束の時間から10分後と30分後、こちらから電話をかけてもみたのだが、「電波の届かないところにおられるか、電源が入っていないため……」という音声メッセージが流れるばかり。その都度、留守電にメッセージを吹き込んでいるものの、徒労感はぬぐえなかった。
「――みたいっすね……」
はす向かいのソファにだらしなく身を投げ出しているイトウくんが、ヤマダくんの独り言めいたつぶやきにぼんやりと相槌を打つ。こちらも、声に疲労感が滲んでいた。
2022年1月下旬――。
ヤマダくんの1軒目のシェアハウス『バーデン-H』のリビングであった。ヤマダくんのソファの隣には、幼い娘を同居するアオノ家に預けてわざわざ駆けつけてくれた妻が、所在なげにちょこんと腰かけていた。管理会社の担当者は、この日は都合がつかなかったため、来ていない。もともと、半ばサービスのような入居面接の立ち会い業務には熱心なほうではなかったから、今後も彼の参加は期待できそうになかった。オーナー夫婦が来ているのだから、せめて挨拶に顔くらい見せたらよさそうなものだが……。
(――まあ、彼の不在はどうでもいい。それより、問題は……)
ヤマダくんは声に出さずに考えをまとめる。そう――問題は、この日この時間(正確には、30分以上前)に訪れるはずだった入居希望者が、一向に姿を見せないことだった。一度や二度なら、「まあ、そんなこともあるか……」と諦めもつく。だが、入居希望者に面接をドタキャンされたのは、これで三度目だった。
一度目は、面接予定日の前夜に電話連絡があった。相手は30代の派遣社員で、電話口でしきりに申し訳なさそうに理由を告げてきた。何でも、その日の朝になって翌月以降の派遣先が決まり、その会社が『バーデン-H』からだと通勤に2時間以上かかるので、急遽別のシェアハウスを探すことにしたのだという。無論、ヤマダくんは事情を快諾し、新しい引っ越し先が無事見つかりますように、と陰ながら祈ったものだった。
二度目は面接当日、それも約束時間になってからだったが、一応電話連絡があった。相手は20代の学生で、理由も言わず、ただ「今日そちらへは行けなくなった」と一方的に告げてきた。さすがにヤマダくんも怒りを覚えたが、さすがに電話口で怒鳴りつけるようなことはなく、わかりましたとだけ言って通話を切った。本音を言えば、説教の一つも言ってやりたいところだったが、言ったところで相手には伝わるまい。
そして、この日が三度目だった。電話連絡どころか、前もって交換していたLINEのアドレスにメッセージを入れても既読すら付かない。完全に無視されていたと言っていい。せっかく、前回は都合がつかなかった妻が同席しているというのに、だ。もっとも、すっぽかした相手にとっては知ったことではないのだろうが……。
――約束の時間を1時間過ぎたところで、ヤマダくんはあきらめて腰を上げた。相手が来ない以上、面接はお流れだ。いつまでぐずぐずしていても仕方がない。
「もう、帰るか――」
妻にそう声をかけ、ヤマダくんがコートに片袖を通したところで――不意に、玄関のチャイムが鳴った。
反射的にイトウくんが立ち上がりかけ、ヤマダくんと一瞬、眼が合った。
「――いいよ。どうせ、ついでだ」
ヤマダくんはそのまま、コートを羽織りながら玄関へ向かう。ここの居住者でこそないが、オーナーであるヤマダくんが来客の応対をしても問題はあるまい。出入りの業者か、郵便配達か。さもなければ、新聞か何かの訪問営業だろう。適当にそう見当をつけて、ヤマダくんは玄関のドアノブに手をかけて、外へ呼びかけた。
「はい……どちら様?」
「あ、はい――あの……」
途端に、ぜいぜいと息切れしたかすれ声が返ってくる。
「あのッ! わたし、今日……ッ!」
懸命に息を整えようとしているらしいが、何を言っているのかよく聴き取れない。とりあえず、ドアチェーンをかけたまま、ヤマダくんは細めにドアを開いて外のようすを覗き見た。
玄関ポーチの照明の下に、小柄な人影がうずくまるように立っていた。両膝に手をつき、肩が激しく上下している。ここまで全力疾走してきた直後のようだ。
ドア越しに怪訝そうに見ているヤマダくんに気づいて、人影は顔を上げた。顔の半分を覆うマスクのせいで判然としないが、パッと見の印象は20歳そこそこ、下手をすれば10代にも見える女性――ヤマダくんの第一印象としては“少女”だった。誰か、悪い奴に追われてでもいるのか――そう思ったヤマダくんは、とっさに背後を見回してみたが、少なくとも視界の範囲内にそれらしい影は見当たらなかった。
「――どうしました?」
“少女”を怯えさせないように、ヤマダくんは努めて穏やかな口調で問いかけた。
とはいえ――この時点で、ヤマダくんは彼女の正体におおむね見当をつけていた。
(……約束に1時間も遅刻してきた面接者――なんだろうな、やっぱり。たしか、もう少し年はいってたと思ったが――そういえば、勤め先は大学とか言ってたような? 大学生だったっけ? 気まずいもんで、そのへんから走ってきたのか……?)
さんざん待たされたせいで、この日の面接者のプロフィールはあやふやだった。しかし、いくら入居者に早く決まってほしいと言っても、約束を守れない人間は基本的にこちらからお断りだ。ルーズな人間は信用できない。冷たいようだが、それがビジネスの鉄則だった。だから、ヤマダくんはあいかわらずドアチェーンをかけたまま、彼女の返答を待った。
「……あの! わたし! 今日の3時からお約束をいただいているッ……!」
「3時?」
ヤマダくんは思わずそう訊き返した。そんな約束は知らない。今日の約束は、事前に何度も確認した通り、13時からであった。ヤマダくんたちは念の為、12時半過ぎからスタンバっていた。今は14時過ぎである。
「何かのお間違いでは?」
重ねてそう訊き返したのは、多少意地の悪い気持ちもなかったとはいえないだろう。相手が13時と午後3時をカン違いしていたのだということは、ここまでのやりとりでヤマダくんには想像がついていた。悪気はなかったのかもしれないが、やはり、そういうケアレスミスをする相手は信頼性に欠ける。
「ああッ!!」
“少女”がドアの向こうで大声を上げた。騒々しい奴だな、とヤマダくんはますます心証を害した。やはり、門前払いが吉だろう、と思う。
だが、遅刻してきた面接者は執拗だった。
「あの! すいません! これには! 訳があるんです!!」
ヤマダくんが覗いていたドアの隙間に指先をかけて、彼女は叫ぶように訴えてきた。とんでもない相手だった。
「どうぞ、お引き取りください」
冷ややかに言って、ヤマダくんはドアを閉めようとする。が、相手が指をかけているのでドアが閉まらない。力任せに引っぱれば、指を挟んで大ケガをするに違いない。まったく、厄介な相手だった。
――と。
玄関先での騒ぎを聞きつけて、イトウくんたちがリビングから出てきた。ドア越しのやりとりは、リビングでもはっきり聞き取れたようで、事情は察している顔つきだった。
「――ちょっと。ご近所迷惑よ」
冷静にそう言ったのは妻だった。あきれ顔をしてヤマダくんを見つめる。
「いいじゃない。まだ帰る前だったし――」
その声が耳に入ったのか、ドアの外の“少女”が勢いづく。
「あの! 話だけでも! 話だけでも聞いてください!!」
ヤマダくんは心底ウンザリした表情を浮かべた。妻の背後には、イトウくんもやれやれといった顔で頷いているのが見えた。実質3対1では分が悪い。ヤマダくんは仕方なく、ドア越しに声をかけた。
「わかった、わかった。とりあえず、いったんその手を離して……」
形勢の変化を察して、“少女”はおとなしくドアの隙間から指を抜いた。すかさず、ヤマダくんがドアを閉める。一瞬、そのままカギを締めて踵を返そうかと思ったヤマダくんだったが、さすがにイトウくんや妻の見ている前ではそうもいかない。あきらめてドアチェーンを外し、ドアを開いて“少女”を招き入れることにした。
――1時間遅刻して現れた彼女は、サヤマと名乗った。間違いなく、今日の13時に面接の約束をしていた相手だった。10代にも見まがう童顔と、玄関先での子どもじみた騒動の印象から、ヤマダくんはてっきり相手を学生だと思い込んだものだが、案に相違してアラサーの社会人だという。
リビングに通された彼女は、すっかり落ち着きを取り戻していた。してみると、先ほどの醜態は、想定外の事態にパニクっていたものか。
「××大学で研究員をしております」
改めて身分を告げたサヤマさんを、ヤマダくんはまじまじと見た。なるほど、大学の職員なら、周囲に学生も多いだろうし、自然と立ち居振る舞いも学生めいてくるのかもしれない。
いわゆる“リケジョ”――理系女子という奴らしい。頭脳は優秀かもしれないが、あまり世間ずれしていないようだ。女性研究員などと聞くと、化粧っけのないひっつめ髪に白衣にメガネ、みたいなイメージがあるが、こうして正面から観察すると、年齢相応の大人の女性らしいメイクとファッションに身を包んでいることがわかった。
遅刻の理由について、サヤマさんは問われるままにスラスラと説明した。といっても、特別な事情があったワケではないらしい。研究室での仕事――この日は休日だったが、進行中の実験の都合で短時間でも毎日顔を出さなければならない用事があるらしい――が予定外に長引き、慌てて飛び出してきたのでスマホを実験室に置き忘れてしまったそうだ。ハウスの電話番号や約束の時間も、スマホにメモしてあったのでウロ覚えだったという。それで、電話連絡もできず、おまけに13時か午後3時か迷い、さらに『バーデン-H』の正確な住所もわからないまま、あちこち駆けずり回って、いろいろな人に道を聞き、ようやく訪ね当てたのだという。一応、筋は通っているようだが――ヤマダくんはどうも釈然としなかった。
(――仮にも30歳近い社会人が、そんなことで仕事が務まるんだろうか……?)
そんな印象がふいに好転したのは、イトウくんがこんな質問をした時だった。
「――それにしても、スマホもなしによくここにたどりつけましたね?」
おそらく、何の気なしの質問だったのだろうが、それはヤマダくんも訊きたいことだった。『バーデン-H』をオープンして10年余りになるが、これまでスマホのナビやホームページの地図なしで、ここにすんなりたどりつけた入居希望者は一人もいなかったのだ。
サヤマさんは当たり前のように答えた。
「シェアハウスの立地がわかりにくいのはわりとよくあることなので、駅前の交番で場所を確認してから、ご近所の方にも声をかけて場所を教えていただきました」
「――ほう」
簡単なことのようだが、これは案外できない人間も少なくない。
現代人がスマホのナビなしで知らない土地を歩くと、十中八、九は道に迷う。二、三度通った道でさえ、人によっては迷うくらいだ。何故かといえば、「知らない人に道を尋ねる」ことができないからだという。『バーデン-H』は住宅街の奥まったところにあり、周囲は個人宅ばかりで目印らしきものはない。ピンポイントで探し当てるには、それなりのコミュニケーションスキルが必要になる。
どうやら、彼女はアタマがいいだけでなく、他人と自然にコミュニケーションが取れる人間のようだ。そして――知らない相手と一つ屋根の下で暮らすシェアハウスの住人にもっとも必要なことは、他人とのコミュニケーション能力であることは言うまでもない。
ひと通り面接を終え、肝心の空き部屋に案内する段になったとき――ヤマダくんは、「彼女さえ良ければ入居してもらおう」と、すっかりその気になっていた。
(つづく)
言わでもがなのつぶやきが、無意識に漏れる。苦笑してみせる空元気さえ、湧いてこない。それどころか、文字通り、がっくりと肩を落としてさえいた。何度もくりかえされた失望の念が、いつしか絶望に取って代わったかのように、ヤマダくんは見るからにしょげかえっていた。
――ドタキャンであった。
現われるはずの相手が、約束の時間を30分以上過ぎても現れなかったのだ。電話連絡一本ない。約束の時間から10分後と30分後、こちらから電話をかけてもみたのだが、「電波の届かないところにおられるか、電源が入っていないため……」という音声メッセージが流れるばかり。その都度、留守電にメッセージを吹き込んでいるものの、徒労感はぬぐえなかった。
「――みたいっすね……」
はす向かいのソファにだらしなく身を投げ出しているイトウくんが、ヤマダくんの独り言めいたつぶやきにぼんやりと相槌を打つ。こちらも、声に疲労感が滲んでいた。
2022年1月下旬――。
ヤマダくんの1軒目のシェアハウス『バーデン-H』のリビングであった。ヤマダくんのソファの隣には、幼い娘を同居するアオノ家に預けてわざわざ駆けつけてくれた妻が、所在なげにちょこんと腰かけていた。管理会社の担当者は、この日は都合がつかなかったため、来ていない。もともと、半ばサービスのような入居面接の立ち会い業務には熱心なほうではなかったから、今後も彼の参加は期待できそうになかった。オーナー夫婦が来ているのだから、せめて挨拶に顔くらい見せたらよさそうなものだが……。
(――まあ、彼の不在はどうでもいい。それより、問題は……)
ヤマダくんは声に出さずに考えをまとめる。そう――問題は、この日この時間(正確には、30分以上前)に訪れるはずだった入居希望者が、一向に姿を見せないことだった。一度や二度なら、「まあ、そんなこともあるか……」と諦めもつく。だが、入居希望者に面接をドタキャンされたのは、これで三度目だった。
一度目は、面接予定日の前夜に電話連絡があった。相手は30代の派遣社員で、電話口でしきりに申し訳なさそうに理由を告げてきた。何でも、その日の朝になって翌月以降の派遣先が決まり、その会社が『バーデン-H』からだと通勤に2時間以上かかるので、急遽別のシェアハウスを探すことにしたのだという。無論、ヤマダくんは事情を快諾し、新しい引っ越し先が無事見つかりますように、と陰ながら祈ったものだった。
二度目は面接当日、それも約束時間になってからだったが、一応電話連絡があった。相手は20代の学生で、理由も言わず、ただ「今日そちらへは行けなくなった」と一方的に告げてきた。さすがにヤマダくんも怒りを覚えたが、さすがに電話口で怒鳴りつけるようなことはなく、わかりましたとだけ言って通話を切った。本音を言えば、説教の一つも言ってやりたいところだったが、言ったところで相手には伝わるまい。
そして、この日が三度目だった。電話連絡どころか、前もって交換していたLINEのアドレスにメッセージを入れても既読すら付かない。完全に無視されていたと言っていい。せっかく、前回は都合がつかなかった妻が同席しているというのに、だ。もっとも、すっぽかした相手にとっては知ったことではないのだろうが……。
――約束の時間を1時間過ぎたところで、ヤマダくんはあきらめて腰を上げた。相手が来ない以上、面接はお流れだ。いつまでぐずぐずしていても仕方がない。
「もう、帰るか――」
妻にそう声をかけ、ヤマダくんがコートに片袖を通したところで――不意に、玄関のチャイムが鳴った。
反射的にイトウくんが立ち上がりかけ、ヤマダくんと一瞬、眼が合った。
「――いいよ。どうせ、ついでだ」
ヤマダくんはそのまま、コートを羽織りながら玄関へ向かう。ここの居住者でこそないが、オーナーであるヤマダくんが来客の応対をしても問題はあるまい。出入りの業者か、郵便配達か。さもなければ、新聞か何かの訪問営業だろう。適当にそう見当をつけて、ヤマダくんは玄関のドアノブに手をかけて、外へ呼びかけた。
「はい……どちら様?」
「あ、はい――あの……」
途端に、ぜいぜいと息切れしたかすれ声が返ってくる。
「あのッ! わたし、今日……ッ!」
懸命に息を整えようとしているらしいが、何を言っているのかよく聴き取れない。とりあえず、ドアチェーンをかけたまま、ヤマダくんは細めにドアを開いて外のようすを覗き見た。
玄関ポーチの照明の下に、小柄な人影がうずくまるように立っていた。両膝に手をつき、肩が激しく上下している。ここまで全力疾走してきた直後のようだ。
ドア越しに怪訝そうに見ているヤマダくんに気づいて、人影は顔を上げた。顔の半分を覆うマスクのせいで判然としないが、パッと見の印象は20歳そこそこ、下手をすれば10代にも見える女性――ヤマダくんの第一印象としては“少女”だった。誰か、悪い奴に追われてでもいるのか――そう思ったヤマダくんは、とっさに背後を見回してみたが、少なくとも視界の範囲内にそれらしい影は見当たらなかった。
「――どうしました?」
“少女”を怯えさせないように、ヤマダくんは努めて穏やかな口調で問いかけた。
とはいえ――この時点で、ヤマダくんは彼女の正体におおむね見当をつけていた。
(……約束に1時間も遅刻してきた面接者――なんだろうな、やっぱり。たしか、もう少し年はいってたと思ったが――そういえば、勤め先は大学とか言ってたような? 大学生だったっけ? 気まずいもんで、そのへんから走ってきたのか……?)
さんざん待たされたせいで、この日の面接者のプロフィールはあやふやだった。しかし、いくら入居者に早く決まってほしいと言っても、約束を守れない人間は基本的にこちらからお断りだ。ルーズな人間は信用できない。冷たいようだが、それがビジネスの鉄則だった。だから、ヤマダくんはあいかわらずドアチェーンをかけたまま、彼女の返答を待った。
「……あの! わたし! 今日の3時からお約束をいただいているッ……!」
「3時?」
ヤマダくんは思わずそう訊き返した。そんな約束は知らない。今日の約束は、事前に何度も確認した通り、13時からであった。ヤマダくんたちは念の為、12時半過ぎからスタンバっていた。今は14時過ぎである。
「何かのお間違いでは?」
重ねてそう訊き返したのは、多少意地の悪い気持ちもなかったとはいえないだろう。相手が13時と午後3時をカン違いしていたのだということは、ここまでのやりとりでヤマダくんには想像がついていた。悪気はなかったのかもしれないが、やはり、そういうケアレスミスをする相手は信頼性に欠ける。
「ああッ!!」
“少女”がドアの向こうで大声を上げた。騒々しい奴だな、とヤマダくんはますます心証を害した。やはり、門前払いが吉だろう、と思う。
だが、遅刻してきた面接者は執拗だった。
「あの! すいません! これには! 訳があるんです!!」
ヤマダくんが覗いていたドアの隙間に指先をかけて、彼女は叫ぶように訴えてきた。とんでもない相手だった。
「どうぞ、お引き取りください」
冷ややかに言って、ヤマダくんはドアを閉めようとする。が、相手が指をかけているのでドアが閉まらない。力任せに引っぱれば、指を挟んで大ケガをするに違いない。まったく、厄介な相手だった。
――と。
玄関先での騒ぎを聞きつけて、イトウくんたちがリビングから出てきた。ドア越しのやりとりは、リビングでもはっきり聞き取れたようで、事情は察している顔つきだった。
「――ちょっと。ご近所迷惑よ」
冷静にそう言ったのは妻だった。あきれ顔をしてヤマダくんを見つめる。
「いいじゃない。まだ帰る前だったし――」
その声が耳に入ったのか、ドアの外の“少女”が勢いづく。
「あの! 話だけでも! 話だけでも聞いてください!!」
ヤマダくんは心底ウンザリした表情を浮かべた。妻の背後には、イトウくんもやれやれといった顔で頷いているのが見えた。実質3対1では分が悪い。ヤマダくんは仕方なく、ドア越しに声をかけた。
「わかった、わかった。とりあえず、いったんその手を離して……」
形勢の変化を察して、“少女”はおとなしくドアの隙間から指を抜いた。すかさず、ヤマダくんがドアを閉める。一瞬、そのままカギを締めて踵を返そうかと思ったヤマダくんだったが、さすがにイトウくんや妻の見ている前ではそうもいかない。あきらめてドアチェーンを外し、ドアを開いて“少女”を招き入れることにした。
――1時間遅刻して現れた彼女は、サヤマと名乗った。間違いなく、今日の13時に面接の約束をしていた相手だった。10代にも見まがう童顔と、玄関先での子どもじみた騒動の印象から、ヤマダくんはてっきり相手を学生だと思い込んだものだが、案に相違してアラサーの社会人だという。
リビングに通された彼女は、すっかり落ち着きを取り戻していた。してみると、先ほどの醜態は、想定外の事態にパニクっていたものか。
「××大学で研究員をしております」
改めて身分を告げたサヤマさんを、ヤマダくんはまじまじと見た。なるほど、大学の職員なら、周囲に学生も多いだろうし、自然と立ち居振る舞いも学生めいてくるのかもしれない。
いわゆる“リケジョ”――理系女子という奴らしい。頭脳は優秀かもしれないが、あまり世間ずれしていないようだ。女性研究員などと聞くと、化粧っけのないひっつめ髪に白衣にメガネ、みたいなイメージがあるが、こうして正面から観察すると、年齢相応の大人の女性らしいメイクとファッションに身を包んでいることがわかった。
遅刻の理由について、サヤマさんは問われるままにスラスラと説明した。といっても、特別な事情があったワケではないらしい。研究室での仕事――この日は休日だったが、進行中の実験の都合で短時間でも毎日顔を出さなければならない用事があるらしい――が予定外に長引き、慌てて飛び出してきたのでスマホを実験室に置き忘れてしまったそうだ。ハウスの電話番号や約束の時間も、スマホにメモしてあったのでウロ覚えだったという。それで、電話連絡もできず、おまけに13時か午後3時か迷い、さらに『バーデン-H』の正確な住所もわからないまま、あちこち駆けずり回って、いろいろな人に道を聞き、ようやく訪ね当てたのだという。一応、筋は通っているようだが――ヤマダくんはどうも釈然としなかった。
(――仮にも30歳近い社会人が、そんなことで仕事が務まるんだろうか……?)
そんな印象がふいに好転したのは、イトウくんがこんな質問をした時だった。
「――それにしても、スマホもなしによくここにたどりつけましたね?」
おそらく、何の気なしの質問だったのだろうが、それはヤマダくんも訊きたいことだった。『バーデン-H』をオープンして10年余りになるが、これまでスマホのナビやホームページの地図なしで、ここにすんなりたどりつけた入居希望者は一人もいなかったのだ。
サヤマさんは当たり前のように答えた。
「シェアハウスの立地がわかりにくいのはわりとよくあることなので、駅前の交番で場所を確認してから、ご近所の方にも声をかけて場所を教えていただきました」
「――ほう」
簡単なことのようだが、これは案外できない人間も少なくない。
現代人がスマホのナビなしで知らない土地を歩くと、十中八、九は道に迷う。二、三度通った道でさえ、人によっては迷うくらいだ。何故かといえば、「知らない人に道を尋ねる」ことができないからだという。『バーデン-H』は住宅街の奥まったところにあり、周囲は個人宅ばかりで目印らしきものはない。ピンポイントで探し当てるには、それなりのコミュニケーションスキルが必要になる。
どうやら、彼女はアタマがいいだけでなく、他人と自然にコミュニケーションが取れる人間のようだ。そして――知らない相手と一つ屋根の下で暮らすシェアハウスの住人にもっとも必要なことは、他人とのコミュニケーション能力であることは言うまでもない。
ひと通り面接を終え、肝心の空き部屋に案内する段になったとき――ヤマダくんは、「彼女さえ良ければ入居してもらおう」と、すっかりその気になっていた。
(つづく)
シェアハウス大家さん倶楽部について
新着コンテンツ
-
第144回 2026年とシェアハウス
2026-1-15 -
第143回 変化の時代とシェアハウス
2025-12-19 -
第142回 光明とシェアハウス
2025-11-17 -
第141回 抵抗感とシェアハウス
2025-10-16 -
第140回 未来予想図とシェアハウス
2025-9-16 -
第139回 不動産市況とシェアハウス2025夏
2025-8-16 -
第138回 公的支援とシェアハウス
2025-7-15 -
第137回 変わらぬ魅力とシェアハウス
2025-6-16 -
第136回 「不都合な真実」とシェアハウス
2025-5-16 -
第135回 時の流れとシェアハウス
2025-4-17
〜シェアハウス事業を企画から運営まで、トータルにサポート〜
運営会社:株式会社シェアスタイル | シェアハウス資産運用のご相談はこちら | シェアハウス管理物件のご紹介はこちら | 採用情報
Copyright © 2006-2015 ShareStyle Co.,Ltd. All Rights Reserved.